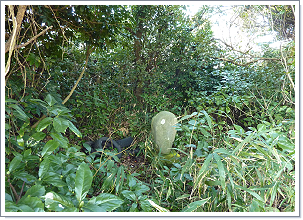伯耆国 八橋郡
のつじょう
箆津城

所在地
鳥取県東伯郡琴浦町箆津
城 名
のつじょう
箆津城
箆津村への所在に因む
別 名
まきじょう
槇城
槇氏の築城に因む呼称
築城主
槇氏
築城年
不詳
廃城年
不詳(天正年間(1573年~1591年)と推定される)
形 態
丘城、海城
遺 構
郭跡※、切岸、土塁、空堀、虎口※、土橋※、櫓台
※ 大部分が畑地へ改変
※ 平入虎口
※ 平入虎口へ接続
現 状
畑地、原野
備 考
琴浦町指定文化財(昭和50年6月2日)※赤碕町指定文化財として登録
縄張図
箆津城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供
城 主
六波羅探題
糟屋重行
幕府方として当地を所領する
城 主
名和
赤坂幸清
糟屋重行の退去後、城主とされる
箆津敦忠
赤坂幸清の後任とされる
城 主
伯耆山名
槇氏
伯耆民談記では一族累々の家城とあり箆津敦忠の戦死後、箆津氏に代わって所領を得たか
参考資料(史料及び文献、郷土史など)
田蓑日記[衣川長秋 著](文政5年9月 弘所書林)
因伯古城跡図志下 伯耆国(文政元年 鳥取藩)
伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)
伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)
伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)
因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)
赤碕町誌(昭和49年11月 赤碕町誌編纂委員会)
新修 中山町誌 上巻(平成21年3月 中山町誌編集委員会)
姓氏家系大辞典 第三巻 ナーワ(昭和38年11月 角川書店 太田亮 著)
日本歴史地名大系第32巻 鳥取県の地名(1992年10月 平凡社)
年 表
文永年間~弘安年間
文永の役(1274年(文永11年))、弘安の役(1281年(弘安4年))の二度にわたる蒙古襲来の脅威から元寇に対する海岸線の防衛拠点として築城された城砦群のひとつと考えられている。
1333年
元弘3年 / 正慶2年
船上山の戦いに敗北した糟屋重行は伯耆国から逃れたとされる。
糟屋重行は後に近江国で佐々木清高らと共に自害したとされ、糟屋重行の退去後は名和方の赤坂幸清、箆津豊後守が領有したと推測される。
1359年
正平14年/延文4年
6月19日(旧暦5月23日)
箆津豊後守が勝田川の戦いで戦死し、その後は槇氏を領主と伝える。
永正年間
永正年間、槇氏と藤井氏が争い、剣が野合戦では藤井氏の家臣、岡部七郎が討死とする。
天正年間
天正年間中に廃城と伝えられる。
概 略
北側に日本海を見下ろす台地先端に所在する。
東側は切岸状の絶壁、東側から南側には勝田川と黒川が天然の川掘となるためか、土塁などの防御施設はなく櫓台と思われる郭跡のみが残存し、台地から地続きとなる西側にのみ空堀、土塁、虎口、土橋など防御施設を配置している。
因伯古城跡図志 箆津村古城跡
箆津村古城跡野原端也。草木有。高十五間、下ハ海、東側川有。西側堀切、海辺ニ少ノ灘付。東西通有。四十五町沖ハ大松有。
赤碕町誌(一部抜粋)
城の内(じょうのうち)と呼ばれ堀跡、土塁跡が残る。近くの畑には建物の礎石と思われる石が点在する。文政年間(1818年~1829年)の古地図には二町四方の地域を有したとある。元弘3年(1333年)の船上山合戦の後、名和氏の軍勢に攻められ焼討された当時の伯耆国守護代糟屋弥次郎の居城、中山城とする説、地域狭小で守護の居城としない説がある。城跡の近くには「剣が野(つるがの)」「御立山」「カジ山」「牧戸」の地名があり城との結びつきを残す。「剣が野」では永正の頃(1504年~1511年)に藤井氏の岡部七郎が討死し、その亡霊が残っていて往来の人を悩ましたと伝えている。付近には古墳も散在している。槇の城から約1Km半、箆津部落の東のはずれの墓地(字陣場)に箆津豊後守敦忠の墓がある。
赤碕町誌では元寇(1274年(文永11年)の文永の役、1281年(弘安4年)の弘安の役と二度にわたる蒙古襲来)に対する海岸線の防衛拠点として築城されたことが始まりと推測される一方、鎌倉時代に糟屋重行の持ち城であった説、戦国期に槇氏が築城したとする説など諸説が見える。
姓氏家系大辞典 第三巻(田蓑日記より)
八橋郡箆津城は箆津豊後の拠る所。
姓氏家系大辞典 第三巻
和名抄、伯耆国八橋郡に箆津郷を收む。後世、野津邑と云ふ。この地より起こりにして退休寺は1354年(正平9年)、箆津敦忠の建立地と。
箆津の地名の由来と併せて退休寺についても触れられているが、退休寺の建立時期については1357年(延文2年)とする説も見える。
箆津氏(野津氏)は伯州衆の一角として名が挙げられている。(大舘常興書礼抄)
伯耆民談記 槇城の項
安田郷箆津村にあり。槇氏代々居す。永正の頃かとよ、藤井何某か家人、岡辺七郎当城に攻寄せ今云ふ剣ノ野に於て大いに戦ひ討死す。其亡霊残りて往来の人を悩す事、暫く累年に及ぶと云へり。此野に七の塚あり。是、首塚とも、又、七塚とも云ふ。一つは岡辺七郎か首塚、残る六は従卒の塚と云伝ふ。剣ノ野以西の金谷村にある大地を金谷野とも云ふ。此野は槇、藤井、多年の戦場にして千戈をちりはめし処なる故、剣ノ野と称すかや。(中略)又、件の藤井某は今の信州上田の城主、松平伊賀守忠国の先祖なるか。是、本姓藤井氏なり。長臣代々岡辺七郎と云ふ。今は九郎兵衛と云へり。
伯耆民談記 御立山の項
東西半道、南北一里余許り、平々たる広野なり。野中に領主の立山(禁伐林)あり。大なる松原にて南北三丁許り。東西十四丁に足る。
永正年間(1504年~1521年)頃
槇氏と藤井氏の争いが続き、藤井氏の家臣であった岡辺七郎が剣ノ野で戦死とある。
岡辺七郎の亡霊が近隣住民を悩ませたとも伝えている。
天正年間(1573年~1591年)頃
新修中山町誌上巻では築城年不詳、廃城年は天正年間と推測し、槇氏代々の居城とする説を伝承の域を出ないとしている。
写 真
2016年1月16日