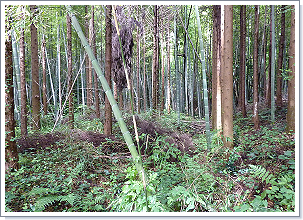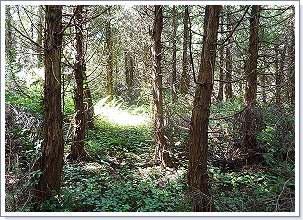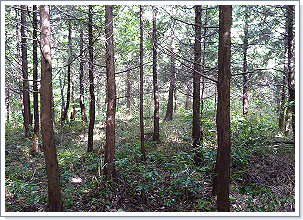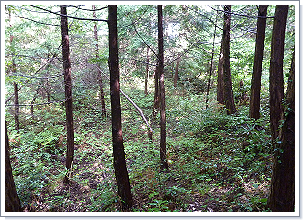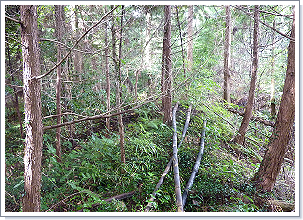伯耆国 汗入郡
いわいがきじょう
石井垣城

所在地
鳥取県西伯郡大山町赤坂、鳥取県西伯郡大山町潮音寺
城 名
いわいがきじょう
石井垣城
伯耆民諺記に記述
別 名
いわいがきじょう
岩井垣城
伯耆民諺記に記述
なかやまじょう
中山城
太平記や異本伯耆巻などに記述
ちょうおんじじょう
潮音寺城
因伯古城跡図志に潮音寺村古城跡と記載
あかさかじょう
赤坂城
名和世家に記述され八橋郡赤坂村諸事書上帳では赤坂村に古城が所在とする
なかやまくだりまつのしろ
養中山下リ松ノ城
村社春日神社社格昇進願の記述
築城主
山中幸盛
尼子再興戦での築城を伝える
築城年
不詳(船上山の戦い以前の築城)
廃城年
不詳
形 態
複郭式平山城
遺 構
郭跡※、土塁、空堀、虎口、堀切、切岸、門跡※、石塁、土橋、馬出、櫓台、城主墓所※
※ 本丸、二ノ丸を含む区画と春日神社、古代墓地に別れる
※ 二ノ丸居館区に残存とする
※ 箆津豊後守の墓と伝える
現 状
山林、春日神社、果樹畑
備 考
史跡指定なし(字御墓の峰は大山町の町有地)
縄張図
石井垣城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供
(遺構名称加筆)石井垣城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供
城 主
六波羅探題
糟屋重行
伯耆守護代とする
糟谷元覚
伯耆守護代とする
城 主
名和
赤坂幸清
糟屋重行の追放後の城主とする
箆津敦忠
赤坂幸清の後任とする
城 主
伯耆山名
箆津信清
箆津敦忠の子孫とする
参考資料(史料及び文献、郷土史など)
異本伯耆巻
金勝寺本 太平記
名和氏紀事
大館常興書札抄
汗入郡万覚帳
田蓑日記[衣川長秋 著](文政5年9月 弘所書林)
因伯古城跡図志下 伯耆国(文政元年 鳥取藩)
伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)
伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)
伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)
因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)
赤坂神社明細帳
村社春日神社社格昇進願(1900年(明治33年))
八橋郡村々諸事書上帳(岩井垣村諸事書上帳、赤坂村諸事書上帳 1862年(文久2年))
汗入史綱(昭和12年9月 国史研究部 本田皎)
中山町史
新修 中山町誌 上巻(平成21年3月 中山町誌編集委員会)
新修 中山町誌 下巻(平成21年3月 中山町誌編集委員会)
大山町誌(昭和55年10月 大山町誌編さん委員会)
名和町誌
船上山史
赤碕町誌(昭和49年11月 赤碕町誌編纂委員会)
新修米子市史
名和世家 平泉 澄 著(昭和29年(1954年)1月 日本文化研究所)
姓氏家系大辞典 第三巻 ナーワ(昭和38年11月 角川書店 太田亮 著)
中世城郭事典
日本歴史地名大系第32巻 鳥取県の地名(1992年10月 平凡社)
年 表
1333年~
元弘3年/正慶2年~
赤坂幸清が京都へ向かった前後、在地土豪の箆津敦忠が入城し、以後は箆津氏累々の居城と伝わる。
また、赤坂幸清は入城せず糟屋氏滅亡直後から箆津敦忠が城主とも伝える。
概 略
汗入郡と八橋郡の境界に所在する。
且つての石井垣村内に所在したことに因み一般的には「石井垣城」と記される。
伯耆民諺記では「岩井垣城」と記述されており、伯耆民談記が改変されていく過程で併用されている部分も見える。
別名を「中山城」とし、甲川岸沿いの小規模な要塞で糟屋氏の館の西北に逢坂八幡宮が所在したと伝える。
伯耆国では珍しい複郭式の構成を持つ大規模な城だが歴史については不明な点が多い。
伯耆民談記 岩井垣の城の条
一、岩井垣の城
中山郷岩井垣村にあり。箆津豊後守敦忠数代相伝の家城なり。敦忠は有福の士にて退休寺の開壇なり。この仏閣の巻に誌し置く所なり。敦忠の墓は箆津の竹林にあり。此近村に悟正院長音寺と云う村あり。昔時、岩井垣の城下隆盛の時は高閣寺院あり。然るに彼の城亡廃の後、兵火に炎滅して遂に退転して今は寺院もなく只寺号を村名に称する計り也。
伯耆民談記 退休寺の条
一、退休寺 八橋郡退休寺村 禅宗能登国惣持寺末山 寺領二十七石
金龍山と号す。本尊は観音、代々国守より建立の地なり。開壇は当郡岩井垣の城主、箆津豊後守平敦忠。延文二年の草創にして開山は玄翁和尚也。当国に於て稀なる大寺なり。
伯耆民談記 糟屋氏の条(昭和35年3月 萩原直正校註)
相州糟屋氏の族で当国の守護代、船上山北二里、中山城に拠る。
伯耆民談記では伯耆の糟屋氏の条に記述が見え、後に箆津氏の家城であったと記述されている。
糟屋氏は相模国の一族で伯耆国守護代へと就き、船上山から北二里の「中山城」に拠ったとしている。
1205年(元久2年)
伯耆国の守護職は金持六郎広親、「名和氏紀事」では守護代を糠屋弥次郎重行入道元寛としている。
太平記 異本伯耆巻
金勝院本に云、大手の寄手命を殞とす者其数をしらず。残る所の勢共、当国の守護、糟谷弥二郎入道元覚が中山の城に楯籠たりしを行氏信真以下究竟の兵を率し間をも透さず只攻に攻ければ云々。
元亨年間
赤坂掃部が伯耆国細木原城へ居城。赤坂掃部は赤坂幸清とする。
元弘年間
城主を糟屋弥二郎入道元覚としている。(名和氏紀事、金勝寺本太平記にも同様の記述が見える)
金勝寺本太平記では糟屋弥二郎入道元覚を別に明翁と注記があり、六波羅探題では重鎮とする。
に伯耆守護職、糟谷弥二郎入道元覚を城主とする。
諸文献や古記録の記述に見える「中山城」は当城か伯耆国箆津城(槙城)が推定されている。
1333年(元弘3年/正慶2年)
船上山の戦いで幕府方の追討軍に勝利した名和長年の逆襲を受け、伯耆国小波城に続いて当城も攻められ炎上し落城と伝える。(幕府方の糟屋元覚は64歳で自刃し一族は滅亡とする)
城主であった糟屋氏滅亡後の当城の動向については諸説存在する。
・名和長年に与した赤坂幸清が当城へと入るが後に京都大宮で討死する。その後は在地土豪の箆津敦忠が入城し以降は居城とする。(時期としては赤坂幸清が京都へ発つ際に後任を任されたか)
・赤坂幸清は入城せず糟屋氏滅亡直後から箆津敦忠を城主とする説。
因伯古城跡図志 伯耆国 潮音寺村古城跡
潮音寺村古城跡、箆津豊後守の居城と申伝え高十五間にして山にて無之野続也。草木有。後通り二丈位の切崖下は甲川有。
此所橋跡有。以前堀の形、当時田地也。
因伯古城跡図志では「潮音寺村古城跡」と記されることから別名に「潮音寺城」とも呼称される。
城の周囲に張り巡らされた堀に関しては「堀長三十間、全幅二間位」「同九十間位」「幅二間位」とあり、三重の堀から西の外側には更に堀跡を残した田地と橋の跡があると記されている。
城の大手は「表酉」と記載され、西側に虎口跡が見られる。元来は木橋が架かっていたと推測されている。
現在は春日神社を含む範囲を城域としているが、古城跡図志の記録者は春日神社(春日大名神)を城域に含んでおらず、当時は主郭(本丸及び二ノ丸)周辺のみを城域として認識していたことが伺える。
そのため西側の墓地区画とされる郭跡も城跡に含めていない。
八橋郡赤坂村諸事書上帳
村より八丁南、字城ノ内と唱え、箆津豊後守様古城之跡御座候。堀数々墓所五輪等は御座候へ共(略)
八橋郡赤坂村諸事書上帳には赤坂村に箆津豊後守の古城が所在したとしている。
箆津敦忠は奈良から春日大明神を勧請※したことが春日大明神由緒に見える。(八橋郡村々諸事書上帳)
※名和長年が勧請し建立したとする説も見える
箆津豊後守の伝承として箆津敦忠を金龍山退休寺の開基としている。(新修 中山町誌(下))
赤坂集落内には赤坂掃部の居館が所在したと伝えるが、記述の見える郷土史では既に消滅とある。(汗入郷土誌)
村社春日神社社格昇進願では当城の事を「養中山下リ松ノ城」としている。
城に関する字名には「城ノ内」「上城ノ内」「下城ノ内」「天馬河原」「御墓ノ峰」が見られる。
墓地区画(字御墓ノ峰)に「ふるさとフォーラムなかやま」の建築計画もあったが、地元有志の陳情及び保存運動によって施設建物は城域外の現在地へと計画が変更されたため、墓地区画は大山町の町有地となったが史跡指定は受けていない。
写 真
2014年2月22日、2014年9月14日、2014年9月21日