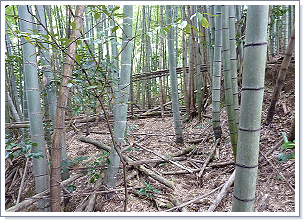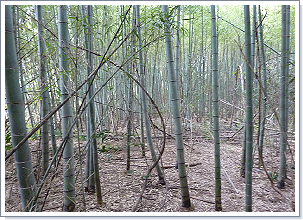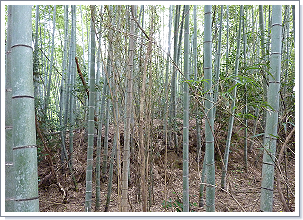伯耆国 日野郡
ふるでらいくまつじょう
古寺生松城

所在地
鳥取県西伯郡伯耆町二部(字古寺生松)
城 名
ふるでらいくまつじょう
古寺生松城
「ふるでらおいまつじょう」とも呼称
別 名
にぶようがいじょう
二部要害城
周辺の城砦をまとめた総称
にぶどいやまじょう
二部土居山城
伯耆志での呼称
築城主
不詳(後藤実基が推測される)
築城年
不詳(天寧山傳燈寺の建立と同じ頃と推定される)
廃城年
不詳
形 態
平城
遺 構
郭跡、腰郭、帯郭、土塁、切岸、虎口、櫓台、空堀※
※ 竪堀、堀切、横掘の何れかとする
現 状
山林、畑地
備 考
史跡指定なし
縄張図
古寺生松城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編)米子城略測図より抜粋)※鳥取県教育委員会提供
城 主
藤原
後藤実基
天寧山傳燈寺の建立と併せて城郭の築城を伝える
後藤基清
兵火によって荒れ朽ちた天寧山傳燈寺を再建した際に併せて城郭も建造とする
参考資料(史料及び文献、郷土史など)
伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻五 大正5年11月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
日野郡史 前篇(昭和47年4月 日野郡自治協会)
日野郡史 中篇二(昭和47年4月 日野郡自治協会)
溝口町誌(昭和48年9月 溝口町誌編さん委員会)
ふる里 野上の郷(平成11年12月20日 溝口町二部公民館 著)
溝口町制施行40周年記念 文化財ガイドブック ふるさと溝口(1993年 溝口町教育委員会編)
年 表
1162年
応保2年
後藤左衛門尉実基が二部奥の地(二部宿字中寺)に寺を移し、天寧山傳燈寺を号する。
1216年
建保4年
天寧山傳燈寺の堂宇、城郭共に兵火によって灰燼に帰し荒れ朽ちていたが、後藤左衛門尉基清によって再建とある。(ふる里 野上の郷)
概 略
郷土史「ふる里 野上の郷」では二部上要害、二部下要害を合わせて「要害山」としており、字「古寺生松城」周辺の丘陵が「土居山」と考えられる。
鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編)では伯耆国二部上要害の北側郭跡を居館跡と推定しているため、二部上要害の所在する場所が「土居山」とも考えられる。
伯耆志 二部村の条 古城の件
一は土居山と称す。事蹟詳ならず。
伯耆志では二部村の条で古城跡のひとつとして記述が見える。
溝口町誌
字古寺生松城にあり。西に面する地。左衛門実基の居城跡と云う。
溝口町誌では城主の左衛門尉実基について官位と諱のみの記述だが、後藤実基(實基)と推定される。
1162年(応保2年)
後藤実基が二部奥の地(二部宿字中寺)に寺を移し天寧山傳燈寺を号している。
1216年(建保4年)
天寧山傳燈寺は兵火に遭い、堂宇、城郭は灰塵に帰し荒れ朽ちていたが後藤左衛門尉基清によって再建とある。
※「ふる里 野上の郷」では”左衛門尉実清が再建するも廃頽”とあるが実基と基清が混同した誤植と考えられ、正しくは左衛門尉基清と思われる。
永禄年間には足羽重成が二部へと訪れ天寧山伝燈寺の外護修復が行われたとある。
足羽氏が周辺に所領を得た頃にも天寧山伝燈寺は廃頽していたとしている。
1573年(天正元年)
織田氏との対立により越前朝倉氏が滅亡したため、朝倉家の家臣であった足羽重成の一族が二部村に入ったとされる。
足羽氏の一族が二部村へ入る経緯や時期には諸説あるが、当地を治めていたと推測される後藤氏の動向はこの頃から不明となる。
写 真
2014年10月12日