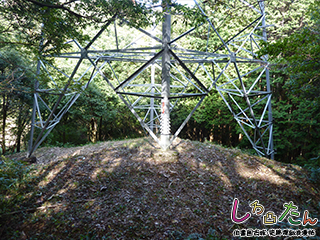伯耆国 日野郡
えびじょう じょうのおまる
江美城 城野尾丸

所在地
鳥取県日野郡江府町江尾(字城ノ尾、字寺ノ段)
城 名
えびじょう じょうのおまる
江美城 城野尾丸
別 名
えびじょう じょうのおまる
江尾城 城ノ尾丸
「城ノ尾」の字名に因む表記
しらおじょう
白尾城
「白尾」の字名に因む呼称で「城尾」の転訛か
築城主
不詳
築城年
不詳
廃城年
不詳
形 態
丘城
遺 構
郭跡※、堀跡、土塁※、切岸※
※ 字「寺ノ段」が居館か
※ 字「寺ノ段」を囲む
※ 字「城ノ尾」付近
現 状
畑地、山林
備 考
史跡指定なし
縄張図
字城ノ尾周辺図(江尾全図 ※一部着色)※江府町役場提供
参考資料(史料及び文献、郷土史など)
陰徳太平記[香川正矩 編](明治44年5月 犬山仙之助)
雲陽軍実記[河本隆政 著](明治44年11月 松陽新報社)
伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻四 大正5年10月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
因伯古城跡図志下 伯耆国(文政元年 鳥取藩)
伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)
伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)
伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)
因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)
萩藩閥閲録(森脇覚書、三吉鼓家文書)
吉川広家功臣人数帳(1617年)
大日本古文書(大正15年 東京帝国大学文学部史料編纂所 編)
出雲文庫第三編 和譯出雲私史(大正3年9月、大正13年9月第2版)
江府町の文化財探訪問<第1集>(平成元年3月 江府町教育委員会)
江府町史(昭和50年12月 江府町史編さん委員会)
江尾全図(昭和50年5月 江府町)
新修江府町史(平成20年6月 江府町史編纂委員会)
日野郡史 前篇(昭和47年4月 日野郡自治協会)
江府町報 縮刷版(昭和56年1月 鳥取県日野郡江府町役場)
江府町報 第52号 江美十七夜物語(昭和46年9月10日 井上中山香)
新修鳥取県神社誌 因伯のみやしろ(平成24年6月 鳥取県神社誌編纂委員会)
江美城銀杏段丸跡試掘調査報告書(平成13年3月 江府町教育委員会)
新鳥取県史 古文書編下 古代中世Ⅰ 東伯耆(平成27年3月鳥取県立公文書館県史編さん室)
年 表
概 略
伯耆国江美城南側の出丸(宇佐木丸)から白尾谷を隔てた南側の丘陵、字「城ノ尾」に所在を伝える。
江美神社社記では藤井内蔵頭の居城と伝えている。(江美神社社記)
字「城ノ尾」周辺が主郭と伝えられ、北側に隣接する字「出屋」には方形区画が残存する。
西側は字「入江」と伝え、往時の日野川の流路が現在より内陸側に迫っていたことを伺わせ、天然の川堀或いは湿地帯として利用したと推測される。
主郭西側に相当な高低差を持つ切岸を配しており、特に西側から南側に対する防御を備えた城郭であったと考えられる。
字「出屋」には土居或いは居館が置かれたと仮定すると、字「城ノ尾」が詰城と推測されるが、字「白尾入口」を挟んだ北東側には字「寺ノ段(てらんだ)」と伝える四方を土塁で囲まれた台地があり、構造的にはこちらも土居跡と推測される。
字「寺ノ段」の北側にはやや小高い地形が残され、白尾谷を挟んで江美城や宇佐木丸との連携に要する施設(見張台や狼煙台)の存在が推測されることから江美城の城域南限を当城として、往時の蜂塚要害とする呼称は北限とされる銀杏ノ段から南限の当城を合せた大規模な城塞群を表現したとも推測される。
当城を独立した城郭と仮定する場合、同等の規模を持つ勢力の居館が2ヶ所存在した可能性が考えられる。
後述の「江美神社社記」では1536年(天文5年)に蜂塚義光と藤井蔵人の両人が同時期に江美城への居城を伝える伝承があり当時の本城が江美城(城ノ上)或いは銀杏ノ段に続き、当城である可能性も検討に入れる必要性を考えさせられる。
伯耆志 江尾村の条 城跡の項
(略)寺の段、城尾、白尾、小原など云う地あり。皆田土の字なり。何事も詳ならず。
伯耆志では宇佐木丸に続いて地名の記述が見えるが、こちらも既に田畑となり往時の詳細は不詳としている。
城跡の項で宇佐木丸から続いて地名が挙げられていることから筆者が城跡ではないかとして記述した意図が伺える。
江美神社社記の項(日野郡史)
(略)城野尾と申処に藤井内蔵頭御在城にて其家来に相見佐馬之介と申武士、彼の淵に怪魚棲み人を煩すに付、相見佐馬之介退治。これより字を相見ヶ淵と申伝う。
江尾の江美城の項(日野郡史)
日野郡史に収録の江美神社社記では城主に当城の城主、藤井内蔵頭を併記している。
1536年(天文5年)には蜂塚義光、藤井蔵人が現在の江美城に居城としており、藤井蔵人と蜂塚義光が同格に扱われている。
江府町誌にのみ藤井内蔵を蜂塚氏の家老(家臣)としているが、日野郡史からは家臣ではなく同等の勢力をもつ一族であったとも考えられる。
また、江美城の所在を字「城ノ上」としていることから蜂塚氏の拠点が蜂塚義光の頃には銀杏ノ段から移っていたと考えられていたことが読み取れる。
1564年(永禄7年)/ 1565年(永禄8年)
毛利方による江美城攻略戦では銀杏ノ段、宇佐木丸の陥落する描写は見えるが当城は登場しない。
陰徳太平記(巻第三十九 伯州江美之城没落之事)や森脇覚書では江美城への総攻撃が始まると蜂塚方の降伏は一切許されなかった描写が見える。
蜂塚氏滅亡後に江美城の城番として藤江蔵人の在城が見えることから、開戦前より毛利方からの調略を受けるなどして早い段階で降伏し毛利方へ与したことが伺える。
伯耆志では口碑に藤江蔵人が江美城の城番を務めたとしているが江美城全域或いは居城であった当城のみの城番とするか詳細は不明。
銀杏ノ段より西、小江尾の小字にも「城尾(じょうのお)」が見える。
白尾狐の伝説(江府町史 要約)
白尾に留吉という白狐が住んでいた。白狐は神の使いとされ、留吉も神の使いとされた。
夜になると老爺に変身し、村の正直者に施しをする役を言いつかり、真面目に務めていた。
いつか太平山の狐仲間から誘われるがままに遊び回っていて、遊び癖がつき神の言いつけを忘れるようになり、神の怒りを買って元の野狐に色換えをされようとしたが泣いて謝ったので神様の使いは差し止め、胴だけを野狐に塗り替え、足と尻尾だけは白いままで許された。白尾はこれからついた地名である。
留吉という白狐が太平山の狐に唆されたためになまけ癖が付き、神の怒りを買うといった話となっている。
太平山は大山寺を示し、その狐は大山寺の僧であることから大山寺とは何らかの確執があったために白尾の伝説に姿を変え語り継がれたとも考えられる。
写 真
2021年10月30日
東側遠望
字「白尾入口」
字「白尾入口」
水路と石垣
水路と石垣
水路と石垣
虎口
南見張郭
南見張郭
見張郭
見張郭西側
見張郭東側
主郭
主郭
主郭北西切岸
空堀と土塁
空堀と土塁
字「白尾入口」
字「寺ノ段」
字「寺ノ段」
字「寺ノ段」
字「寺ノ段」
2016年12月18日、2016年12月22日