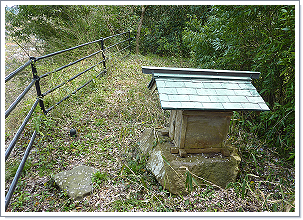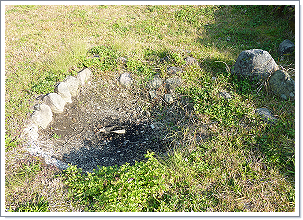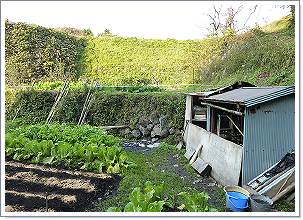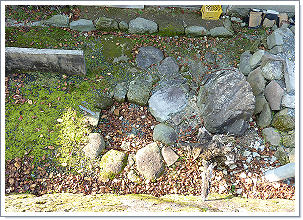伯耆国 日野郡
えびじょう
江美城

所在地
鳥取県日野郡江府町江尾(字城ノ上)
城 名
えびじょう
江美城
城名に関しては江戸期より江美の字を当てる
別 名
えびじょう
江尾城
現在の地名か旧字「古江尾」に因む呼称
えみじょう
江見城
雲陽軍実記に表記があり、往古は「えみ」と呼称している
えびようがい
江尾要害
杉原盛重が鼓右京亮へ宛てた感状に見える江美城の呼称(三吉鼓家文書 永禄七年九月十六日付)
はちつかじょう
蜂塚城
毛利元就が宮景盛へ宛てた書状に見える江美城の呼称(日野文書(永禄七年)八月廿五日付
はちつかようがい
蜂塚要害
毛利元就が山田民部丞に宛てた書状に見える江美城の呼称(山田家文書(永禄七年)八月廿五日付)
築城主
築城年
1484年(文明16年)
廃城年
1611年(慶長16年)頃
形 態
平山城
遺 構
郭跡※、堀切※、空堀※、土塁、桝形※、虎口、列石遺構、桝形虎口、櫓台、土橋※
※ 城ノ上、上ノ段、土井ノ内、寺ノ前、上東屋敷、宮ノ前、馬場、馬場道ノ下など
※ 東側の土橋から以南の字名が「堀切」であり城ノ上の南側を巡る
※ 東側の土橋から以北、東祥寺の墓地や観音像が所在する場所の字名はヲクビとなる
※ 人桝とも呼ばれ、本丸の西側~西の丸北直下に所在
※ 近年の造作物であり城ノ上の水田へ引水する為に埋め立てたもので本丸に残存した櫓台南側部分や礎石、石材を埋めて造成とする
現 状
畑地、水田、山林、上之段広場、江美神社、東祥寺、山村開発センター、江府町民俗資料館 他
備 考
江府町指定史跡(平成7年5月16日指定)
縄張図
江美城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供
宮氏の家臣とされる荒木氏の一族か
毛利方の占領後、城番として置かれた武将のひとり
佐々木四郎太郎
吉川広家功臣人数帳で城主とする
城番として置かれた武将のひとり
参考資料(史料及び文献、郷土史など)
陰徳太平記[香川正矩 編](明治44年5月 犬山仙之助)
雲陽軍実記[河本隆政 著](明治44年11月 松陽新報社)
伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻四 大正5年10月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
因伯古城跡図志下 伯耆国(文政元年 鳥取藩)
伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)
伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)
伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)
因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)
萩藩閥閲録(森脇覚書、三吉鼓家文書)
吉川広家功臣人数帳(1617年)
大日本古文書(大正15年 東京帝国大学文学部史料編纂所 編)
出雲文庫第三編 和譯出雲私史(大正3年9月、大正13年9月第2版)
米子史談(佐々木謙)
江府町の文化財探訪問<第1集>(平成元年3月 江府町教育委員会)
江府町史(昭和50年12月 江府町史編さん委員会)
江尾全図(昭和50年5月 江府町)
新修江府町史(平成20年6月 江府町史編纂委員会)
日野郡史 前篇(昭和47年4月 日野郡自治協会)
江府町報 縮刷版(昭和56年1月 鳥取県日野郡江府町役場)
江府町報 第52号 江美十七夜物語(昭和46年9月10日 井上中山香)
新修鳥取県神社誌 因伯のみやしろ(平成24年6月 鳥取県神社誌編纂委員会)
角川日本地名大辞典 31 鳥取県(昭和57年12月 角川書店)
新鳥取県史 古文書編下 古代中世Ⅰ 東伯耆(平成27年3月鳥取県立公文書館県史編さん室)
年 表
1524年
大永4年
1562年
永禄5年
毛利氏が出雲国への侵攻を開始すると伯耆国内の国人衆が相次いで尼子氏から離反する。
尼子方であった本城常光の寝返りを機に蜂塚義光も毛利方へと属する。
12月1日(旧暦11月5日)
毛利方に降った本城常光が殺害される。
1564年/1565年
永禄7年/永禄8年
9月6日/8月26日(旧暦8月1日)
美保関より吉川方の船団が出航するが荒天に遭い福良、外江の港へ四日間停留し、破損した舟の修理を行っている。
9月10日/8月30日(旧暦8月5日)
吉川方の部将、山縣四郎右衛門、屋葺四郎兵衛らにより居館が放火され蜂塚義光らは詰城へ移動する。
9月11日/8月31日(旧暦8月6日)
毛利方の杉原盛重、山田満重、吉川方の今田上野介、二宮木工助、森脇右衛門尉ら総勢3,000騎を以て総攻撃が開始される。
9月13日/9月2日(旧暦8月8日)
蜂塚義光は一族とともに自刃し落城とある。
※文書(三吉鼓家文書、日野文書など)では永禄7年(1564年)、軍記物(陰徳太平記、雲陽軍実記など)では永禄8年(1565年)の出来事としている。
永禄年間~天正年間
概 略
鉄山の経営(鉄穴及び製鉄)と開田の技術(開墾及び稲作)に長けた日野郡の在地国人衆(日野衆)、蜂塚氏の一族で蜂塚安房守による草創を伝える。
鳥取縣神社誌(宮市神社由緒)
往古より若一王子権現と称う。紀伊国熊野より勧請せしこと社伝旧記に見ゆ。
昔時此地の豪族進氏の崇敬厚く、其後文明年中蜂塚安房守江尾在城以来二代三河守、三代丹波守、四代右衛門尉に至る迄八十餘年間崇敬厚く、社領高十三石六斗五升三合寄附せらる。
永禄八年八月蜂塚氏吉川駿河守に亡ぼされ、為めに社領を失い社殿等も荒廃するに至る。
1484年(文明16年)
通説では蜂塚安房守による草創と唱えられているが、宮市神社の社伝では同年に蜂塚安房守が在城とするのみで築城には触れられておらず、これより以前(進氏の頃か)の築城とも推測される。(鳥取縣神社誌 宮市神社の項)
日野郡史 前編 江尾の江美城の項
日野郡史 前編 江美神社の項
所在地 江美村大字江尾字銀杏ノ段。石上神宮勧請磐船神社と唱へ後、王子権現と称す。
大正四年五月二十三日、上の段へ移転。旧城址名によりて江美神社と改む。
江美神社社記(日野郡史 前編収録)
本村より十町許り上に方り、入江といふ所にあり。銀杏の大樹があった事から是に因み銀杏の段といふ也。尚、蜂塚氏の旧城は唯今学校の上なる土地を古城といふ。又、唯今学校の敷地は土器(居の誤字か)の内と申して今、字を土居の内と申す也。寺の處より上を馬場といふ。又、西の門坂と申は蜂塚氏御在城の時、西の御門趾なるを以て字を西門坂といふ。
1536年(天文5年)
日野郡史では蜂塚氏の居館を字「土居ノ内(江尾全図の表記は土井の内)」、古城跡を字「城ノ上」としており、この年までには本城が銀杏ノ段から移転し蜂塚義光、藤井蔵人が城主としている。
江美神社の旧所在地は字「銀杏ノ段」とし、蜂塚義光は城内の王子権現で武運長久の祈祷を受けたとしていることから1536年(天文5年)以前は本城が銀杏ノ段に所在とする認識であったことが読み取れる。
字「城ノ上」に所在した城郭は毛利氏による統治の頃、吉川氏が政庁として新たに築城、増改築を行ったと推測され、所在地や移転時期に関しては近年再考されている。
伯耆志 江尾村の条 小祠の項
村の東北方五十間の山地にあり。磐船山と呼ふ。祭神又勧請等の事社伝に続々説あれとも悉無稽の妄談なり。但し旧地にて天正元年の棟札に吉川駿河守元春の名あり。次に元和元年の棟札あれとも偽作と見えたり。以後は興禪公より御代々の御名を記す。慶長六年、中村氏の臣、小松勝三郎、桜甚吉の社領証文あり。高六石并居屋敷云々とあり他の文字滅して読がたし。
伯耆志では磐船神社の祭神や勧請について社伝の記述は全くの出鱈目とし、元和元年の中村一忠の名が見える棟札も偽物としている。
伯耆志 江尾村の条 城跡の項
東祥寺の上の山なり。尼子氏の草創なり。陰徳太平記に曰く、伯耆江美城主蜂塚右衛門尉は先年尼子を背て毛利家の命令を請たりしか本庄父子か誅せられし時より又志を返して本の尼子の幕下に成ぬ。かくて富田城中勢衰へて頼むかひなく成けれは蜂塚か一族共今は早尼子の為に義を建たりとも行末に於て其の益無るへし。只、再毛利家へ降参の縁を求められ候へと諫言を納れたりけり。されとも蜂塚は吾累年の好みを忘れ毛利家に腰を折つるさへ思へは志士義人の耻る所なるに。さらは其のままにて有りも果てす。又本の尼子に帰服せし事是又千悔万悔なり。然るに尼子の滅亡近きにあるへしと見て又弱を捨強に附ん事、人間の色身を受けたる物は為さざる所にして禽獣夷狄の心とや云うべき。かかる時節に至て貞節を守り討死したらんこそ。せめて旧悪を少しは蓋う便りともなる可し吾(原本此所江尾古城図有省略之)
義心爰に極れり。命惜く妻子も不便に思はんとする者共は悉く毛利家に降り候へ。士は渡り物なり。何そ恨とも思ふへき吾は一人たりといへとも当城を枕として善道の死を守るへきなりと云ひけれは家の子郎党共皆此儀に心服し一向に討死と思切て居たりけるを去程に蜂塚尼子の旧盟を不変とかく戦死せんと儀定して在る由聞えける間吉川元春より杉原播磨守盛重に彼城攻落すへき由下知せられ検使として今田上野介、二宮木工助、森脇市郎右衛門、山縣四郎右衛門等を差添られにけり。各永禄八年八月朔日、雲州三保関より舟に取乗り押渡らんとしける時節俄に狂風吹来り迅雨盆を傾けて振出怒潮海岸を穿ち雲霧山を掩ふて暗く舟己に覆らんとしける故。力不及漕戻し、福良、戸ノ井に四日滞留して討損せられし舟共修補して同五日又押渡りけり。其夜半、山縣四郎右衛門、屋葺四郎兵衛等を相伴ひ蜂塚か館へ押寄せ放火したりけるに敵は皆館を明捨て城中に籠り居ける故可防者一人も無りけり。翌朝、寄手三千餘騎城の左右の山頂に攀登り鉄炮を揃へ散々に撃掛ける間雑兵共堪兼て城外へ颯と崩れ出けるを追詰一人も不残打取けれは蜂塚はとても叶はしとや思ひけん腹搔切て失にけり。杉原、今田、二宮等は数百人の首を捕て気色はふて帰ける處に元春、各江美城攻取事は粉骨の忠なりといへとも大風暴雨に舟とも無理に出し多くの兵をも失んとせし事甚奇怪の曲事なりと以ての外に憤り給ひ今田、二宮、森脇、山縣等四十五日か程は出仕をそ止られけるとみえたり。此の後の事詳ならず。口碑には蜂塚氏の後、生山某一代、荒木刑部一代、今田左衛門尉、其後吉田佐太郎、藤江蔵人なと云う人在城せし由云伝う。東祥寺の側に成道寺と呼ぶ地あり。古墳あれとも伝なし。
陰徳太平記 巻之三十九 伯州江美之城没落之事
伯耆国江美ノ城主、蜂塚右衛門尉は先年尼子を背いて毛利家の命令を請けたりしが本庄父子が誅被ずるより、又志を反へして本の尼子の幕下と成りぬ。如斯て富田城中、勢い衰えて頼むかい無く成りければ蜂塚が一族共今は早や尼子の為に義を建てたりとも行末に於て其益無かるべし。只再び毛利家降参の縁を求められ候えと諫言を納れたりけり。され共蜂塚は吾累年の好みを忘れ毛利家に腰を折りつるさえ思えば志士義人の耻ずる所なるに、さらば其ままにて有も果不。亦本の尼子に帰服せし事是又千悔万悔也。然に今尼子の滅亡邇在可(ちかくなり)と見て復た弱きを捨て強きに附かん事人間の色身を受けたる者は成不所にして猛禽夷狄の心とや云うべき。かかる時節に至りて貞節を守り討死したらんこそせめて旧悪を少しは葢う便りともなるべき吾れ疑心爰に極まれり。命惜しく妻子も不便に思わんずる者共は悉く毛利家に降り候え。士は渡り物なり。何ぞ恨みとも思うべき。吾は一人たりと雖(いえども)、当城を枕として善道の死を守るべきなりと云ければ家の子郎党皆此儀に心服し一向に討死と思い切つてぞ居たりける。去程に蜂塚尼子の旧盟を變不(かえず)、兎角戦死せんと議定して在る由聞えける間吉川元春より杉ノ原播磨守盛重に彼の城攻め落すべき由下知せられ検使爰に今田上野介、二宮木工助、森脇市郎右衛門、山縣四郎右衛門等を差添をれにけり各永禄八年八月朔日雲州三保ノ関より舟に取り乗り押し渡らんとしける時節俄に猛風吹き来り。迅雨盆を傾けて降り出て怒潮海岸を穿ち雲霧山を掩うて暗く舟巳に覆らんとしける故、力及不漕ぎ戻し福良、戸之井に四日滞留して打損せられし舟ども修補して同五日又押渡りけり。其夜半、山縣四郎右衛門、屋葺四郎兵衛等を相伴い蜂塚が館へ押寄せ放火したりけるに敵は皆館を明捨て城中に籠り居ける故。防者一人も無りけり可。翌朝寄手三千餘騎城の左右の山頂に攀じ登り鉄炮を揃へ散々に撃掛ける間、雑兵共堪え兼て城外へ颯と崩れ出でけるを追い詰め一人も残不打取りければ蜂塚はとても叶わじとや思ひけん腹搔き切て失せにけり。杉ノ原、今田、二宮等は数百人が首を捕りて気色ばって帰りける所に元春、各江美ノ城攻め取る事は粉骨の忠也と雖、大風暴雨に舟共無理に出し多くの兵を失わんとせし事甚だ奇怪の曲事也と以の外に怒り給い、今田、二宮、森脇、山縣等四十五日が程は出仕をぞ止られける。
雲陽軍実記 雲州国士及於毛利再為尼子方事の条
雲陽軍実記 毛利所々人数置 并再富田発向端城落る事の条
伯耆国江美城主、蜂塚右衛門尉は先年毛利に降りけるが全く本意に非ず。当時の急難を逃れん為なりとて。又尼子へ帰り無二の志を成しけるが毛利より杉原に下知して城を被攻(せめられ)けるに今田上野介、二の宮杢之助を探り使として被差向(さしむかわされる)。合戦花々敷有けるが小勢にて難渋に及びしかば右衛門尉さわやかに鎧ひ出立終に潔く討死して名を後代に残しける。
和譯出雲私史 巻之五 尼子氏上 義久の条
(永禄)八年三月、元春、隆景等来つて富田の麥(麦)を取らんとす。我兵出でて之を拒ぎ、敵敗れ還る。
四月十七日、元就、衆を悉し三面より来り攻む。元就、輝元は御子守口(或は尾小森口に作るは誤なり。以下の三口は皆富田城の門名)に向い、元春、元長は鹽谷口に向い、隆景は菅谷口に向う。義久、二弟倫久、秀久と同じく城を出でて接戦す。倫久は元春に当り、秀久は隆景に当り、而して自ら元就に当り、殺傷相当る。元就曰く「堅城勅敵未だ力争す可らざるなり」と二十八日、洗合に引き還る。
蜂塚右衛門尉、我が為に伯耆の江美城を守る。
杉原盛重感状 (三吉鼓家文書)
毛利元就書状 (日野文書 新鳥取県史収録)
宮上総介 御陣所 毛利右馬頭元就
就、今度日野衆逆心、御帰路之方々、或被立御用、或至富田被因。数輩御越渡候。於去八日、蜂塚城、御親類両人御討死候。旁以御心中奉察。我等迷惑此事候。此等之儀、更不知所謝候。仍太刀一腰、具足一領、甲一刎進入候。乏少之至候。猶、赤川十郎左衛門尉(就秀)可申入候。恐々謹言。
(永禄7年)八月廿五日 元就 宮上総介殿 御陣所
毛利元就書状 (山田家文書 新鳥取県史収録)
山田民部丞殿 元就
其表永々在番候て辛労之をこそ存候処。今度日野郡敵心付。而、心遣之段不及申候。雖然其方種々以短息気遣。馬田七郎右衛門尉引成。蜂塚要害切崩、則時被郡仕返候。粉骨之段、不知所謝候。連々付可有忘却候。猶、赤川十郎左衛門尉(就秀)可申聞候。 謹言。
(永禄7年)八月廿五日 山田民部丞殿 元就
1524年(大永4年)
伯耆民談記では、尼子経久による伯耆国侵攻(大永の五月崩れ)を受けた際、蜂塚氏が尼子家に取り立てられたとしている。
しかし、日野郡は伯耆山名氏の影響下にあった頃からも尼子方へと与する国人が多く、当城の創建或いは蜂塚氏の台頭(進氏からの独立)には尼子氏の後ろ盾を得たことにより成し得た側面も伺えることから、当城の草創を伝える1484年(文明16年)頃には既に尼子方へと与していたと推測する方が自然と考えられる。
伯耆志では当城の創建を尼子氏によるものとしていること、伯耆民談記の大永の五月崩れでは落城した伯耆国内の主要諸城に当城が含まれていないことから元来より尼子方の勢力であった説の補強材料となる。
1561年(永禄4年)
毛利氏の勢力が伯耆国へ及ぶに至り、伯耆国内の国人衆の多くが尼子氏を見限り毛利氏へと靡く中、尼子方の重臣であった本城常光の降伏を機に蜂塚義光も毛利方へ恭順する道を選んでいる。
1562年12月1日(永禄5年11月5日)
毛利氏に降った本城常光らの殺害が伯耆国へと伝わると、先に毛利方へと恭順した尼子方の国人衆の多くが再び離反し尼子方へ与する事態となっている。
蜂塚義光も1562年(永禄5年)末頃から1563年(永禄6年)の間に再び尼子方へと帰順しており、日野郡での一連の騒動を「日野(衆)の逆心」とする。
陰徳太平記でも伯耆国人衆の寝返りの原因は本城父子の誅殺に起因するものとしており、毛利方の対応が悪手であったことを暗に綴っている。
蜂塚義光は尼子方から毛利方へと一度は忠を曲げたが、再び尼子方へと与し最期を迎えたことから主家に対して忠節を尽くした忠義の将とされ、敵将であったにも関わらず毛利方から高い評価を受けている。
雲陽軍実記では毛利方へ寝返ったことは不本意なこととし、周辺情勢を鑑みた上での苦渋の決断であったとしている。
1564年(永禄7年)/ 1565年(永禄8年)※
出雲国月山富田城攻略の一環として伯耆国側からの支援拠点であった当城に対して吉川元春は毛利方の杉原盛重を総大将として攻略に向かわせている。
同年7月下旬から8月1日までの間に杉原盛重が率いる毛利方の本隊は当城周辺へと到着し、本陣の設営や調略などの工作を行っていたと推測されるが委細については描写がなく不明である。
伯耆民談記では岸本村の安国寺付近を通過の際に安国寺の僧、祖権による妨害を受けている。
森脇覚書や山田家文書(毛利元就書状)では杉原盛重の本隊へ伯耆国河岡城から山田満重、日野文書(毛利元就書状)では伯耆国生山城から宮景盛の増援があったとしている。
吉川元春は杉原盛重への検使として島根半島に駐屯していた今田上野介、二宮木工助、森脇市郎右衛門、山縣四郎右衛門らに派兵を命じている。
1564年9月6日 / 1565年8月26日(永禄7年8月1日 / 永禄8年8月1日)※
吉川方の増援部隊は美保関を出航するが暴風雨のため計画通りの渡海が行えず、無理な渡海により多くの人的、物的損害を出した上で出雲国福良港や伯耆国外江港などへと流されており、退避した船団は破損した船舶の修理などで4日間程の足止めを受けている。(陰徳太平記、伯耆民諺記)
1564年9月10日 / 1565年8月30日(永禄7年8月5日 / 永禄8年8月5日)※
舟の修理を終えた吉川方の船団が再度出航し同日の夜半には主戦場へと到着する。
同日夜半から明け方には吉川方の部将、山縣四郎右衛門が屋葺四郎兵衛を伴い城主の居館へと放火しているが蜂塚義光や守将らは既に詰城へと移動した後で無人であったとしている。
1564年9月11日 / 1565年8月31日(永禄7年8月6日 / 永禄8年8月6日)※
毛利方本隊の杉原盛重、山田満重、吉川方増援部隊の今田上野介、二宮木工助、森脇右衛門尉ら総勢3,000騎を以って蜂塚義光の立て籠もる当城本丸への総攻撃を開始する。
日野川岸や城下に布陣していた吉川方の増援部隊は銀杏ノ段と兎丸を占拠し、左右の山上から射撃、銃撃を行い蜂塚方の将兵の逃亡を許さず主郭へと押し留めている。
伯耆民談記では攻撃開始から同日のうちに落城し、蜂塚義光も即日自刃としている。
1564年9月13日 / 1565年9月2日(永禄7年8月8日 / 永禄8年8月8日) ※
城主の蜂塚義光は一族とともに自刃し落城する。
自刃の前に残った将兵の降伏を嘆願したとされるが許されず全員が殺害されている。(森脇覚書、三吉鼓家文書(永禄7年9月16日付杉原盛重書状)、陰徳太平記、伯耆民諺記)
三吉鼓家文書の杉原盛重より鼓右京亮に発給された感状では「鞁右京亮」と見え、「鞁石右亮」と訳している書籍も見える。
また、一部欠歟ヶ所はあるが粟根東市介へ宛てた同様の書状が存在するとある。
※古文書(三吉鼓家文書、日野文書など)では永禄7年(1564年)、軍記物(陰徳太平記、雲陽軍実記など)では永禄8年(1565年)の出来事としている。
江府町報 第52号に収録の江美十七夜物語では陰徳太平記を基として戦闘の詳細や登場人物の活躍が物語として追記されている。※作者の井上中山香は江府町長 井上健治氏のペンネーム
創作のため陰徳太平記の内容と相違する部分や架空の人物も登場するが江府町史編纂事業に伴ったもので入念な考証の上で発表がなされている。
物語では蜂塚義光の自刃の場面が本能寺の変を髣髴とさせ、妻のお市の方の武勇も目を見張る。
城下での戦闘に於いては今田経高と屋葺四郎兵衛の武勇が特に大きく扱われている。
今田経高は銀杏ノ段の櫓付近へと潜み放火の機会を伺い、占拠した後は東門から宮市坂にかけてお市の方と激しい戦闘を行っている。(陰徳太平記では山縣四郎右衛門と屋葺四郎兵衛が近い行動を取っている)
屋葺四郎兵衛は独立した軍団長の扱いとなり、兎丸対岸の向山に布陣すると上は相見ヶ谷、下は伯耆国美女石城に至るまで日野川岸に沿って長大な陣を展開させると水路上の退路を断ち、最後まで手綱岩に上って戦闘を行ったなど肉付けがなされている。(陰徳太平記では山縣四郎右衛門の部将とする)
江美十七夜物語の他、兵隊作家であった棟田博氏が「江美城落城」という小説を週刊誌に発表したとも伝え聞く。
陰徳太平記では1565年8月26日(永禄8年8月朔日)からの出来事とされ、検使であった吉川方(美保関の増援部隊)からの視点となっている。
このため戦闘の詳細は増援部隊の到着する8月5日夜半からの記述となり、それまでの杉原盛重が率いた毛利本隊や他の増援部隊の動きは不明となっている。
毛利方本隊に参加したとする武将にも伯耆国内に於ける杉原盛重直属の部将が見えないことから、同時期に伯耆国八橋城の攻略、あるいは戦後処理に部隊を割いていたと推定するなら永禄8年とする設定は整合性が取れる。
落城を1565年(永禄8年)とする説の補強としては第二次月山富田城の戦い(1565年~1566年(永禄8年~永禄9年))に於いて未だ伯耆国側からの補給線が健在であり、月山富田城へは山中の間道を使い兵糧を運ぶことが可能であったとされている。
同年4月、毛利方による月山富田城への総攻撃も伯耆国側からの支援により士気を維持した尼子方は毛利方を撤退しているため、現時点で当城と八橋城が健在と推定するなら1564年(永禄7年)の落城は考え難くなる。
包囲戦の失敗から伯耆国内に補給拠点が残存している状態で月山富田城は落ちないと判断した毛利方は先に伯耆国内に残る尼子方の拠点制圧と補給線の寸断を進めることとなる。
同年8月、蜂塚義光が守る当城が陥落し山中の間道(陸路)が寸断されている。
同年9月、尼子方の吉田源四郎が守る八橋城が陥落し日本海側の航路が毛利方へと掌握されている。
当城と八橋城の落城時期には諸説あり、八橋城の落城は同年初夏(5月~6月頃)とする説も見える。
当城或いは八橋城の落城を以て伯耆国内で尼子方に与する主要拠点が消滅し、伯耆国側から月山富田城への兵站が封鎖されている。
同月、再び包囲戦を開始し兵糧攻めを以って翌年の1566年(永禄9年)11月に月山富田城を攻略している。
伯耆民談記 江尾城の条
古戦書に日野郡江美城と云うは此江尾城の事なるべし。当城は本柳原村にあるとも云えたり。
伯耆民談記に見える「本柳原村」が何処を示しているのかは不明だが、現在の小江尾で往時に「古江尾」とする地域と考えられている。
字名にも「城尾」が見え、原初の当城本丸とされる銀杏ノ段の属城とする古城の存在が推測される。
日野郡史では四代目、蜂塚義光が治めた頃(永禄年間)の本丸は天文年間中に銀杏ノ段から字「城ノ上」或いは字「上ノ段」へ移転としている。
移転時期には諸説あり、蜂塚氏の滅亡後に吉川氏が領有し字「城ノ上」へ移ったとする説、伯耆国内で大きな戦争がなくなった頃に近世城郭へと改修された頃の移転とする説の他、毛利方に攻められ落城する前後の永禄年間は未だ銀杏ノ段が本丸とする説も見える。
毛利方の文書では「蜂塚城」や「蜂塚要害」とあり、銀杏ノ段、兎丸、城ノ尾丸、天狗ヶ滝など一帯を含めた広域な城砦と認識されていたと考えられるが、この頃の銀杏ノ段を本丸とするには一部疑問が残る。
陰徳太平記では今田上野介らの増援部隊が日野川岸或いは城下に布陣しているため、この視点から「左右の山頂に攀じ登り…」とする場合、当城の本丸を中心とするならば左の山が銀杏ノ段、右の山が兎丸と推定するのが妥当と考えられる。
銀杏ノ段を本丸とする場合、左の山を古江尾の城尾、右の山を当城或いは兎丸とも置き換えられるがやや距離が開く。
山頂から鉄砲で撃ち掛けたとしている点については当時の火縄銃の有効射程距離から銀杏ノ段の山頂からでは当城の本丸まではやや届かないことも考えられるため、字「銀杏ノ段」の範囲で少し下って舟谷川の川岸辺りから射掛けたと推測される。
射撃位置を山頂に拘らない場合、銀杏ノ段も古江尾の城尾と当城の本丸で挟撃する形は可能だが、更に距離が開くため城砦を利用した射撃戦を行ったとすることは考えに難くなる。
但し、鉄砲については「鉄炮」と記されており、広義であるが火縄銃の他に大筒や大砲も含まれるため、射程距離による問題はなくなる。
当城(字「城ノ上」)を本丸とする場合、西に日野川、北に舟谷川、小江尾川、南に南谷川、奥市川が流れる舌状台地突端に所在しており、現在と流路が変わっている可能性はあるものの各河川を天然の川堀として利用できる。
古文書では「江見(えみ)」、陰徳太平記でも「江美(えみ)」と記されることからも各河川を見渡せる位置に所在した事が読み解ける。(河川を見渡せる点では銀杏ノ段にも当てはまることで、西に日野川、北に小江尾川、南に舟谷川を川堀として利用できる)
大山寺方面へ続く東側台地に対しては巨大な空堀(字「堀切」)を東から南にかけて配することで防御力を高めていたことが残存する地形から伺える。(昭和の始め頃に工事を行ったり埋めたとする手記や口伝があり、相当の改変を受けたとする)
現在の東祥寺が所在する位置から更に東には成道寺(成導寺、清洞寺)の所在が字名から伺え、成道寺と東の空堀を以って比較的手薄な東側の防衛力を強化していたことが推測できる。
江府町史では江美神社の旧所在地を字「清導寺」とし、同じく東側の防御施設であったと想定している。
城主の蜂塚氏は古くから続く伯耆国日野郡の国人とされ、1524年(大永4年)の大永の五月崩れ以降に尼子氏と誼を通じたとしている。
当城の草創とされる1484年(文明16年)頃の日野郡は日野衆が独自勢力を維持するなど伯耆山名氏(宗家)の影響力の衰退は顕著であったとする。
1433年(永享5年)には尼子持久によって亀福山光徳寺(現在の鳥取県東伯郡琴浦町公文に所在)へ本堂、庫裡が寄進され寺領への諸役を免除したとする記録が残っており、尼子氏は伯耆国内に於いて重要な拠点のみの点或いは拠点を繋げる線で抑えていた程度とされるが、広く影響力を持っていたことは確かであり、日野郡に関しては砂鉄や銀などを産出できる土地であったことから特に手厚い統治が行われたとする。
文明年間には蜂塚安房守が出現し、日野衆の一翼として蜂塚氏が台頭する頃には尼子氏と深い関係を築いていたと考えられる。
伯耆志 江尾村の条 城跡の項
吉川広家功臣人数帳
江美 佐々木四郎大郎
大日本古文書(二 吉川廣家功臣人數帳(折本) 御用ニ罷立衆)
(伯耆)江美 佐々木四郎大郎(太郎)
1565年(永禄8年)
蜂塚氏の滅亡により周辺一帯が毛利氏の所領となり吉川氏の管轄となるが短期間に城番が変わっている。
蜂塚氏の滅亡直後は宮氏の一族と推測される生山某や家臣の荒木刑部といった日野郡に縁のある人物が城番となり民心の掌握を優先したと考えられる。
軍事面の再編には吉川氏に仕えた今田春倍や今田経高、杉原盛重配下の吉田佐太郎らが留め置かれ、尼子残党の襲来に備えたと推測される。
蜂塚義光と同格に扱われた城ノ尾丸の城主、藤江蔵人も在番したひとりと伝えている。
吉川広家功臣人数帳では佐々木四郎大郎が在番とあり吉川氏の岩国へ転封まで城番を務めたとしている。
蜂塚氏の築いた中世城郭は吉川氏によって近世城郭へと改修が施され、日野川の水運、伯耆往来、日野往来、作州街道など主要な交通網が集約することから宿場町など城下の整備も行われ、日野郡内有数の規模を誇る城郭都市へと変化した事が推測される。
城下町に残る字名には上東屋敷、下東屋敷、上西屋敷、中西屋敷、下西屋敷、新町南屋敷、新町北屋敷、寺ノ前、宮ノ前などが見え、宿場町が栄えた頃は花街の存在も伝わる。
天守台付近(字「城ノ上」)からは伯耆国内唯一(山陰でも唯一)となる金箔鯱瓦の他、桐葉紋軒瓦などが出土している事から当城が豊臣政権下において重要な城のひとつであった可能性が高いと通説では唱えられているが、近年、駿河国駿府城の発掘調査で出土した金箔瓦から、この金箔鯱瓦が当城に据え付けるためのものではない可能性が考えられるようになっている。
旧来の仮説として吉川広家に因む瓦と仮定するのであれば、吉川広家が居城とした月山富田城、或いは築城していた伯耆国米子城に据え付けるため備中方面を経由して予め輸送、保管されていた鯱瓦と推測される。
文禄、慶長の役では普請奉行ら関係者も出征することとなり、本城であった月山富田城の改造や城下町整備に遅延が生じ、米子城の普請も大幅に遅れている。
更に関ヶ原の戦い及び戦後処理により吉川広家が岩国へ移封されるまでに月山富田城の改修或いは米子城が完成を見なかったことから、当城の金箔鯱瓦も保管されたまま忘れ去られてしまったことも考えられる。
吉川氏が保管に気付いていたとしても岩国へ持ち出さなかった理由として、金箔瓦は豊臣家を象徴するものであったことから徳川方に叛意を疑われる可能性を排除するため放置或いは廃棄したことも考えられる。
駿府城の発掘調査で出土した金箔瓦との関連を考えた仮説としては関ヶ原の戦いの戦功で中村氏が駿府から移封の際に何者かが駿府城から持ち出した瓦である可能性も考えられる。
中村方で当城の城番であったとされる人物には林文太夫、矢野正倫と石高の高い重臣の名が見えるが、中村家に関する文書で金箔瓦に触れている記述は現時点で確認されていない。
江尾十七夜の主会場となる字「上之段」の郭跡は1898年(明治31年)3月、旧日本専売公社の工場建設により改変を受けている。
西側の石垣面には2つの抜け穴跡が残り、伝承では蜂塚義光の妻、お市の方が通った隠し通路とする言い伝えが残る。
1980年(昭和55年)に払い下げを受け、現在の上之段広場として再整備が行われている。(江府町史、新修江府町史)
写 真
2013年11月24日、2015年8月28日、2016年4月12日