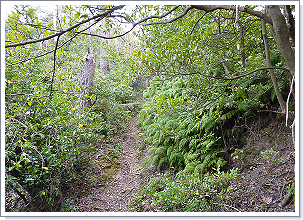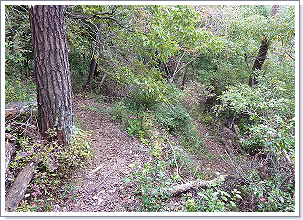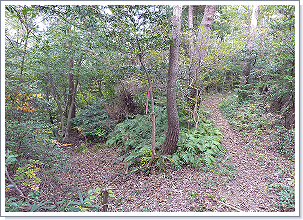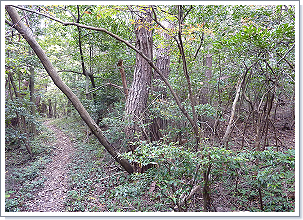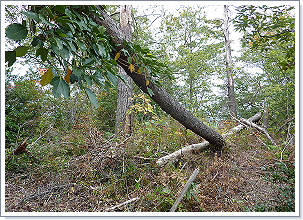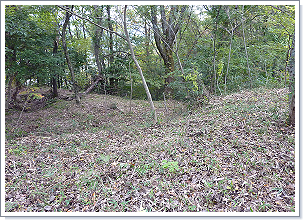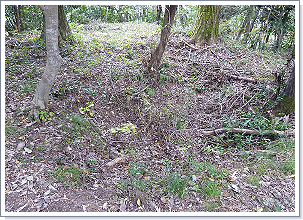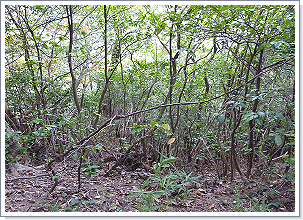伯耆国 会見郡
てまじょう
手間城

所在地
鳥取県西伯郡南部町寺内 他
城 名
てまじょう
手間城
別 名
てまようがい
手間要害
所在する字名に因む呼称
てまのようがいやまじろ
手間要害山城
所在する要害山に因む呼称
てんまんじょう
天万城
所在する地名に因む呼称
てんまんじょう
天萬城
所在する地名に因む呼称
てんまんじょう
天満城
天万、天萬の当て字で因伯古城跡図志や伯耆志では天満山とする
てまこや
手間固屋
手間要害を構成する小規模な砦群のひとつを示す呼称で天万、天萬の当て字も見られる
いわつぼやまじょう
岩坪山城
本丸部分を示す呼称で陰徳太平記などに岩壺山とも
みねまつやまじょう
峰松山城
伯陽闘戦記などの呼称
築城主
日野氏
築城年
不詳
廃城年①
1584年(天正12年) 杉原家内紛での落城を伝える場合は1591年(天正19年)に毛利氏が伯耆国内に領有したのは四城となっており当城は含まれていない
廃城年②
1601年(慶長6年)頃 1591年(天正19年)に毛利氏が伯耆国内に領有した五城のひとつとする場合関ヶ原の戦い前後の維持を伝える
形 態
山城
遺 構
郭跡※、堀切、礎石、土塁、切岸、虎口、櫓台、竪堀、井戸跡※
※ 腰郭、帯郭を伴い主郭付近は連郭、その他魚鱗郭群など
※ 石組の井戸跡が遺り、一部素掘り井戸は風倒木痕も考えられる
現 状
山林
備 考
史跡指定なし
縄張図
手間要害略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供
城 主
伯耆山名
日野氏
▶
尼子
毛利
日野氏
築城時の城主とする
城 主
伯耆山名
日野氏
▶
尼子
▶
毛利
▶
尼子
日野孫左衛門
一時毛利方へ降るが本城常光の粛清の報を受け再び尼子方へと与する
天正10年、毛利方の追討を受けた際に立て籠もったとされる
菖蒲重政
永禄8年頃より城番とされ、天正10年の杉原景盛討伐戦では城将として立て籠もる(陰徳太平記など)
入江大蔵少輔
永禄8年に城番とされる城将のひとり(陰徳太平記)
菊池肥前守
永禄8年に城番とされる城将のひとり(陰徳太平記)
参考資料(史料及び文献、郷土史など)
伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻二 大正5年8月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
陰徳太平記[香川正矩 編](明治44年5月 犬山仙之助)
雲陽軍実記[河本隆政 著](明治44年11月 松陽新報社)
伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)
伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)
伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)
因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)
萩藩閥閲録(山田家文書、小早川隆景書状など)
伯陽闘戦記(文政9年正月 鍋倉村 藤原政五郎の書)
伯耆闘戦記(刊行年不明 ※伯陽闘戦記の写し)
伯耆国陰徳合戦記(天保2年8月刊 ※伯陽闘戦記の写し)
伯耆国陰徳戦記(明治12年写 ※伯陽闘戦記の写し)
天満鎌倉山合戦記(昭和44年1月発行 ※伯陽闘戦記が元)
因伯古城跡図志 下 伯耆国(文政元年 鳥取藩)
会見町誌(昭和48年12月 会見町誌編さん委員会)
会見町誌 続編(平成7年10月 会見町誌編さん企画委員会)
手間要害発掘調査報告書( )
手間要害発掘調査報告書Ⅱ-第2次調査-( )
因伯の戦国城郭-通史編-(1986年 高橋 正弘 著)
米子史談(佐々木謙)
年 表
1000年頃
平安時代
この頃には簡素な建物が猿ヶ馬場付近にあったとされる。
不明
伯耆山名氏の配下、日野氏による築城を伝える。
以後、日野氏の居城であったと推測される。
1524年
大永4年
この頃の城主は日野孫左衛門とされ、大永の五月崩れの後に尼子氏へ降ったと伝える。
1562年
永禄5年
毛利氏が出雲国への侵攻を始めると伯耆の国人衆は相次いで尼子方から離反する。
日野孫左衛門も毛利方へ属したとされる。
12月1日(旧暦11月5日)
尼子方からの降将、本城常光が毛利方により謀殺される。
1563年
永禄6年
本城常光らの殺害が伯耆国へ伝わると、旧尼子方国人の多くが再び毛利方から離反する。
当城の城主、日野孫左衛門も再び尼子方へと属している。
1564年
永禄7年
1565年
永禄8年
毛利方の本隊が伯耆国へ入ったと伝わると城兵は遁走し再び毛利方の所領となっている。
城番には菖蒲重政、入江大蔵少輔、菊池肥前守、守勢に三百騎を付け防衛に当たらせている。(陰徳太平記)
1584年
天正12年
伯耆杉原家の家督争いの収拾後、廃城とされる。※異説有り
不明
伯耆杉原家の改易後は吉田元勝が城主とされる。
関ヶ原の戦いまで伯耆国内の毛利方の主要城砦のひとつとして維持されたと推測される。
概 略
手間山の山頂を中心として「小屋ヶ平」「鐘撞(かねつき)堂」「猿ヶ馬場」などの郭跡群と周辺の山や丘陵に築かれた無数の砦や郭跡群を合わせて「手間要害」と呼称される。
一説には築城の始まりを1,000年頃(平安時代頃)とし、更に時代が遡る可能性があるとも推測されている。
現在も城域の全体像は解明されておらず、鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編)に図志される縄張図で大方1/3程度とされ、数百を超える郭跡群が存在とする。
支城として伯耆国膳棚山城、伯耆国古要害、伯耆国天万固屋、高固屋(絹屋)などの周辺諸城も要害に含まれると考えられ、平時は麓の延命寺居館(伯耆国三崎館)などに居住したと推測されている。
城砦の特徴としては郭内に軍道を通す近接戦に特化した縄張となっている。
また、ほぼ全ての郭が孤立しないよう連携を重視した造りで瞬時に包囲されない限り常に退路が確保できる構造となる。
攻め手にとっては制圧した城砦の多くを維持したままの進軍が必要となるため多くの兵力が必要と攻め難い一方、守り手にとっては城砦間で自由な移動が可能でゲリラ戦も展開しやすく少数でも守り易い城となっている。
従来の説では伯耆山名氏による出雲国を睨んだ城砦(簡素な砦であったとも)が始まりで、尼子氏滅亡後は毛利氏によって大規模な譜請が行われたとする説も考えられていたが、近年の説では伯耆山名氏(日野氏)から尼子氏の頃による築城及び増改築でほぼ完成され、毛利氏による改変は主郭周辺や鐘撞堂の限られた範囲と考えられている。(毛利氏から杉原盛重へ手間の城砦の増強を命じる書状に見える)
道中には出雲国月山富田城にも存在する尼子式の築城技術と似た施設が数箇所現存するが時代は当要害の方が古く、大永の五月崩れ以降に当要害を領有した尼子氏が当城の優れた築城技術を月山富田城へ組み入れたと考える方が自然である。
因伯古城跡図志
天満村の要害で杉原播磨守の居城と申し伝える。大山高山であり会見のこらず日野郡、江尾谷筋、八郷辺のこらず相見える。後のとおり法勝寺谷を請け、険阻にして林有り。近村に竹木有り。山上に赤岩権現の小社有り。山上に水有り、夏は渇水して乏し。山の高さ凡そ百五十間。麓より二百間ばかりなり。
伯耆志 寺内村の条 天万山の項
村の西南五丁許に在て上る事八丁と云へり(略)此地方の高山なり。故に数里の外一望にして指差す山径甚だ険なり。絶頂松林あり。岩坪山と呼ぶ。又、往古城郭ありし故に土人常は要害と呼び、郡中廣くは天満山と呼ぶ。伯耆戦闘記に峰松山とあれども他に考ふる所なし。山上南方に小祠あり。赤岩権現と称す。此処に岩見えず。然れば赤猪石の故事を以て、かく名づけしなるべし。天万山の名、此山を以て主とする故なり(略)其地稍高くして周回二丁許、北方下る事一間許にして又平地あり。周回百間許、此地に井あり。百日の旱魃(かんばつ)に涸るる事なしと云えり。又下る処の平地周回七拾間許南方下る処に又二丁許の平地あり。西北に出櫓と云う地あり。其下に鐘撞堂の跡あり。又其下に猿が馬場と呼ぶ地あり。長八十間、横二十間許なるべし。滑谷(ナメリたに)と呼ぶ。地方に武士の古墳あり。此城何人の草創にや民諺記に大永中、出雲尼子経久数万騎を卒して当国に入り山名の領内、米子、天万、尾高、淀江等の城を攻略し云々と見えて詳なる説なし。然れば此後は尼子氏より兵を籠れしなるべし。伯耆闘戦記に浅野越中守寶光と云う人物、当城に在りて鎌倉山城主戸田安房守と云う人物と戦ひし趣記せるは妄説なる事岡成村の下に記す。かくて永禄八年、毛利氏の大軍出雲に入りし時、当城の兵遁走る尾高城主杉原盛重其部下菖蒲左馬允、入江大蔵少輔、菊池肥前守に三百人を附けてこれに入らしむ(陰徳太平記)爾来、吉川氏の指揮なり。然るに当城を杉原氏の本城とする説あるは甚だ非なり。永禄七年杉原氏、尾高城に入りてより郡中普彼属城たり。民諺記の趣これに同じ。其後、何れの頃廃せしにや詳ならず。当山危岩怪石多し。シヲレ谷と呼ぶ地にて石工常にこれを削る岩坪山の名これに因れるなるべし
1565年(永禄8年)
尼子方の本拠地であった月山富田城を攻略する為、毛利方は主力を出雲国へと向けると当城に拠った尼子方の軍勢は遁走し毛利方の所領となっている。
城番には杉原盛重麾下の菖蒲重政、入江大蔵少輔、菊池肥前守に守勢三百騎を付け防衛に当たらせている。
伯耆志では城番として杉原盛重の重臣が置かれていることから杉原盛重の本城とする説もあるが誤りと評している。
城番配置の指示は吉川元春によるものであり、杉原盛重の本城はあくまで尾高城とする。
伯耆闘戦記や伯耆合戦記の内容についても村芝居の台本程度であり、浅野寶光や戸田安房守といった人物や合戦は創作と評している。
写 真
2014年10月5日、2014年10月19日、2014年11月8日