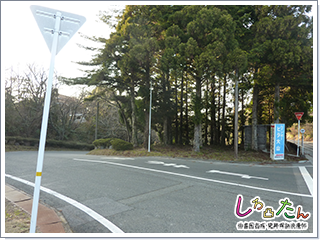伯耆国 会見郡
おかなりじょう
岡成城

所在地
鳥取県米子市岡成 / 鳥取県米子市尾高
城 名
おかなりじょう
岡成城
岡成村に所在することに因む
別 名
おかなりのしろ
岡成之城
岡成地内に所在したとする呼称
おかなりやまじょう
岡成山城
岡成山に所在することに因む呼称
たかまるやまじょう
高丸山城
伯耆志に記述される城名
築城主
不詳
築城年
天文年間(1532年~1555年)
廃城年
永禄年間(1558年~1570年)
形 態
山城
遺 構
郭跡※、空堀※
※ 伯耆志に記述の「高丸山」が不明の為、所在不明とする
現 状
推定地として尾高城の鎌倉時代建物跡、岡成山、岡成神社、岡成池、岡成堤、別荘地
備 考
史跡指定なし
縄張図
不詳
岡成神社以東
岡成池東側
岡成東端
参考資料(史料及び文献、郷土史など)
伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻三 大正5年9月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)
伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)
伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)
因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)
岡成神社縁起書(成立年不明)
伯陽闘戦記(文政9年正月 鍋倉村 藤原政五郎の書)
伯耆闘戦記(刊行年不明 ※伯陽闘戦記の写し)
伯耆国陰徳合戦記(天保2年8月刊 ※伯陽闘戦記の写し)
伯耆国陰徳戦記(明治12年写 ※伯陽闘戦記の写し)
天満鎌倉山合戦記(昭和44年1月発行 ※伯陽闘戦記が元)
尾高の里(昭和52年8月 野口徳正)
尾高の里Ⅱ(発行年不詳 野口徳正)
尾高の里Ⅲ(昭和56年6月 野口徳正)
日本城郭大系第14巻 鳥取・島根・山口(昭和55年4月 株式会社新人物往来社)
米子市埋蔵文化財地図(平成6年3月 米子市教育委員会)
年 表
概 略
伯耆志では岡成村に所在する空堀を有した城郭とされているが正確な所在は判明していない。
伯耆志 岡成村の条 高丸山の項
村より十丁許山麓を回りて至る処の山なり。山下に空隍の形を存す。
正確な所在が不明とする理由は伯耆志の「高丸山」に関する記述に由来する。
伯耆志では岡成村から十丁(約1.2Km)ほど山麓沿いを歩くと山下に空堀が残る場所に出ると記され、此処が高丸山で古城跡としている。
しかし往古から現在にかけ岡成周辺に「高丸山」とする地名は存在しないとする。
そのため伯陽闘戦記などの劇中に登場する城郭とされ、関係する武将や合戦も全て創作としている。
尾高の里(野口徳正著)の岡成神社私考では往古、高丸山の城主某の祈願所として崇敬を受け、高丸山の地名は残っていないが岡成山(岡成より東方の山中)に城跡と思われる参考地があると岡成の人に伝わるとしている。
岡成に「高丸山」の地名は聞いたことがないとする一方、泉に「小丸山」があったとしている。
岡成神社の由緒では城主や配下の武将が城から下って武運長久の祈祷に訪れたと記していることから神社より高所(東側)に所在した可能性が伺え、尾高城とは別の城としている。(但し城主に敬意を示し「城より下った」と表現したとも)
一部の伝承には岡成池西側の岡成堤を元来は尾高城に相対した土塁が始まりとも伝える。
こちらの説を採る場合、当城は大山寺に与する勢力の城砦であったと推測される。
尾高の里では尾高城の支城で後方監視所として大山寺に備えた城であったことが推定されるため相反する説となる。
以上から幻の城とされる当城だが、候補地として岡成地内に4箇所、地外だと2箇所が推定される。
1、伯耆志の高丸山説では地名に「高丸山」が存在しないため「岡成山」とする説。
2、伯耆志に記述の「高丸山より村落迄古の城内」、岡成神社由緒から社殿を含む東側の高地説。
3、岡成堤を尾高城に対する防壁が始まりとする説では堤の対岸に所在する方形の畑地。
4、高丸山説を拡大解釈し「(尾)高(より)丸山(に向かい岡成)村より云々」とするなら現在のペンション村周辺。
5、泉の「小丸山」説。
6、地元では尾高城を「岡成城」と呼称することから、尾高城や鎌倉時代の築城とされる南大首郭付近の建物とする説。
(2)の岡成神社は岡成第3遺跡に含まれ土師器、須恵器の散布密度が高いとあり、(3)の岡成池東岸の方形の畑地は岡成第7遺跡に含まれ試掘の際に土師器数片が出土とある。(米子市埋蔵文化財地図)
伯耆志 岡成村の条 城跡の項
伯耆合戦記、伯耆闘戦記の趣を以て見れは右高丸山より村落迄古の城内と云ふ可し。彼記に曰く岡成山は天文永禄の頃、出雲富田城主尼子氏に附属せし。当郡天萬峰松山城主浅野越中守實光の臣、尾高和泉守重朝が居城なり。織田信長公、松永弾正を亡し給ひし時、浅野氏は戸田安房守森重と共に信長公に属して戦功あり。其後、浅野は伯耆天万の城主となり(所領四万石余)、戸田は同国鎌倉山の城主となる(所領三万石余)(注釈略)永禄元年三月三日上己の賀儀として浅野の臣石田源左衛門、戸田氏に来りけれは戸田の臣、加祥新左衛門是を延て安房守に謁せしむ。安房守曰、汝は牛弓の達者と聞及へり。一見せはやとて牛弓を出されけれは源左衛門畏て庭前の的に向かい一発せしに其矢先に安房守の子息栄次郎至愛の猿飛出て図らすも射止められたり。栄次郎以ての外に立腹しむ。其臣馬場重左衛門に云々命せられけれは重左衛門、源左衛門か後より大身の槍を以て胸板に突通し越しも立す討てけり云々、源左衛門か僕、立帰り右の子細を達しけれは浅野の君臣大に怒り、星川玄蕃、石田帯刀、山根蔵人、坂中丹波等、第一の家老岡成城主尾高和泉守を招き僉儀しけるに所詮、安房守父子来て罪を謝せば免すべし。然らされば討手を遣うへしと評決して寺内彌三郎を使者にて戸田氏に出入けり。戸田氏子細承諾せり。如何にも太刀先を以て是非を極む可しと答へけれは浅野一家彌憤怒し云々。四千四百余騎を出し鎌倉山にそ討寄ける。戸田方には笹畑五郎、能竹隼人、北方鹿之介等云々城外に防戦ふ云々。此軍戸田方大に利を失ひ浅野方は勝鬨挙けて帰りけり。即夜、戸田方天満城に夜討せむと壱萬四千余騎云々。早田飛騨守及び笹畑等搦手に回り火を掛けれは追手の寄手関を作て攻上る云々。城将越中守は岡成城へと志し越城野原を走りけるが早田追付て声を掛け云々。笹畑、鴨部、能竹等続て追来り戦ふ所に浅野方石田帯刀、兼久又兵衛、山根、星川等駈来り云々。戸田方の小田五郎常清と云ふ者、越中守を遥かに見て馬より射落とし遂に首をそ取たりける。石田は主人の首を取返し林の中に埋め置て落行けり。今鶴田の御墓と云ふは是なり。石田、星川、山根、坂中、青木等岡成城に集り岡城五郎云々戸田氏を討んと議しけるか戸田氏返て逆寄にせんとの風間ありけれは井上四郎左衛門奉行にて三日三夜か間に堤成就したりける。五月になりけれは雨降続きて此池恰も海の如し(堤を切て敵を溺らせん為と記せり)。戸田安房守一萬六千余岡成城に押寄せて云々。石田、寺内、兼久等一度に切て出云々。安房守は和泉守か郎党赤松次郎大夫に討る。子息栄次郎森清は当春鎌倉山にて殺されし石田源左衛門か一子、源三郎馬より突落とし親の敵覚えたるかと呼びて首を取る云々。鎌倉方一朝に亡ひしか尾高和泉守天萬鎌倉山共に押領そて勢大に振ひけり。然るに尼子氏の使者来て立退く可き由沙汰の趣申けれは和泉守将卒、稍々落失けれは為ん方無く。上方に走り後は織田氏に仕へけり、其他のものは多く毛利氏に仕へしとかや云々。泉原村は和泉守の居城に隣れる地なるか故の名なり。泉谷も同義なり。尾高支村石田も石田帯刀戦死の地なれは然呼ふ。又、赤松村に赤松次郎大夫か墟あり。又、尾高村も当時迄は高市村と云ひしを和泉守の姓を取て今の名に改む云々。以上原文の大略なり、上件を熟思たるに疑無き偽書なり。其徹を云はば浅野戸田織田氏に仕え松永滅亡の後伯耆に来り永禄元年云々と記す。松永か亡ひたるは永禄元年より廿年後の天正五年なり。齟齬是より大なるは無し。是一、右の一條は推て誤として云はんに二家は尼子氏の部下と聞きたるに三月より五月迄是の如くに騒動するに彼家三里余の近さに在てこれを聞て自若たりしはいかに。是二、安房守森重は杉原播磨を混淆して愚俗を欺くものなる可し。是三、猿を射殺したるを初にして此彼共に亡ひ石田某か仇討の状総て合戦の次第稗史家流の復讐記を学ふか如し。是四、戸田氏一萬六千人を出すと記す。三万余石の管内には男女三萬に足らさるへし。しかれは男一萬五千に過る事多からむ。是を子兒に至る迄悉く招募して猶数に満たす。是五、笹畑弾正、同五郎あり。笹畑村は彼村に長尾氏永禄五年以降開発せし事なれは此時いまた人烟無しいかて弾正なる者あらん。是六、二家の士に尾高、岡成、石田、星川、山根、坂中、兼久、寺内、川岡、青木、赤松、加祥、馬場、早田、笹畑、能竹、鴨部、落合、井上、又名に定常、常清など郡中の村名を以て姓名とする事一篇に満たり義理に難無しと云へとも余に夥しくして返て妄作を著はす。是七、浅野戸田及ひ右に云ふ数人並に事跡とも他の筆記に聊も見たる事なく口碑又灼然たるもの無し。是八、民諺記又陰徳太平記に尾高城を泉山とも記して(注記略)何れをも唱へしものなり。泉原泉谷なとを思ふに此地の惣名なり、二書の趣にては岡成村の山を和泉守の城として泉原は城主の名を取ると記す。既に上の義に齟齬す。然るに高市村を又姓を取りて尾高と改むと云へり。是また妄言なり。此意を察すれは又泉山を云ふか如く続て粉々として治定する所無し。是九なり。然れば鶴田村の墓も附会の談なり。石田赤松の説も同し。嗚呼、何人か妄談を記して兒女を惑はし或はまた正々の眼を費さしむ嘆すへき事なりしかれは縷々記するに足らすと云へ共民間を惑を想れ且姓名の如きは郡中村理の見聞に係るか故に是を弁させる事を得す。前件の如くなれは上の高丸山は何人の古跡とも知り難し。
1558年3月22日(永禄元年3月3日)
伯耆国鎌倉山城にて催された賀儀に於いて浅野實光の家臣、石田源左衛門が遣わされている。
石田源左衛門は弓矢の達人として名が通っており、戸田森重の家臣、加祥新左衛門から余興として弓の腕を披露するよう催促されている。
石田源左衛門は承諾し、的を狙い矢を放つと戸田森清の飼っていた猿が飛び出し不運にもこれを射殺してしまう。
怒った戸田森清は家臣の馬場重左衛門に命じて石田源左衛門を殺害させる。
石田源左衛門の家僕より報せを受けた浅野實光は戸田森重父子が謝罪に訪れ詫びるようであれば手打ちとする意向であったが、戸田方は戦を以ての決着を望んだため浅野方は4,400騎を率いて鎌倉山城へと出陣する。
鎌倉山城での合戦では浅野方が城外へ布陣した戸田方に勝利し、勝鬨を挙げ伯耆国峰松山城へと帰陣している。
同日の晩、浅野方の伯耆国手間城が戸田方14,000騎による夜襲を受け、応戦するも敗走し、浅野實光は伯耆国岡成城を目指し落ち延びる道中、越城野原で追手の小田五郎常清に射殺される。
浅野家旧臣は当城へ集まり戸田森重を討つべく軍議を持ったが、戸田方は更に当城をも落とす勢いであったことから防戦に徹する方針とし、井上四郎左衛門は三日三晩で岡成堤を完成させている。
1558年(永禄元年5月)
岡成池が大海のように湖水を湛えた頃、戸田森重が16,000騎を率いて当城へ襲来する。
伯耆志では戸田森重、戸田森清父子の討死を伝え、浅野家の復讐劇は果たされている。
伯耆闘戦記などでは合戦の詳細が描かれ、浅野方は岡成堤を切り水計を以て戸田方の軍勢を壊滅させている。
戦は尼子氏の仲裁を以て終結するが浅野家、戸田家の両家は滅亡し物語は終幕となる。
当城は創作の城砦とされるが伯耆志、伯耆民談記では実在した他の城砦に比べ多くの情報(伯耆闘戦記などからの引用含む)が記載されている。
登場する人物の名も全てが周辺の地名が元となっており、当城の城主、尾高重朝は地名と尾高城の城主で和泉守を名乗った行松正盛を元にした人物とし、戸田森重は諱から杉原盛重を元にした人物としている。
更に伯耆志では10の理由を挙げ、伯耆闘戦記は妄談、妄作であると酷評している。
岡成城の推定地
高丸山説1(泉の小丸山説)
伯耆志の高丸山説では過去にも現在にも「高丸山」という地名が確認できない。
このため、字「泉」の小字「小丸山」ではないかと考えられる。
大山観光道路を大山方面に向かって進むと道中の左手側の何処かが推定地とされるが、開発が進みそれらしい地形は確認できない。
高丸山説2(岡成山説)
岡成地内で「高丸山」に相当しそうな山は「岡成山」が推定される。
大山観光道路を大山方面に向かって進むと道中の右手側の山中に推定地が所在すると考えられるが、レストランやペンション村の開発によって一部破壊された箇所もあり東端は道路により殆ど削られている。
拡大解釈で「(尾)高(より)丸山(に向かい岡成)村より云々」を採ると写真の位置より手前で南側の谷方面へ進むこととなる。
岡成堤の土壁説(岡成池東側の方形地)
岡成堤の始まりを尾高城に相対するための土壁とする説を採ると岡成池の東側にある方形地の畑が推定される。区画の淵には土塁のような高まりも見え、畑地による改変も考えられるが立地など城跡にふさわしい場所のひとつ。
伯耆闘戦記では三日三晩で急造され、堤を切り戸田方16,000騎を壊滅させたとする。
岡成神社以東説(岡成神社も含む広域城砦説)
岡成神社縁起では城主が城から下って祈祷に訪れたとし、岡成神社を含む以東の高地に城郭があったとする説。
神社から東の山中には小山や段々畑、旧道があり、旧道を更に東へ進むとペンション村に辿り着く。
写 真
2013年6月29日、2015年11月12日、2019年1月14日