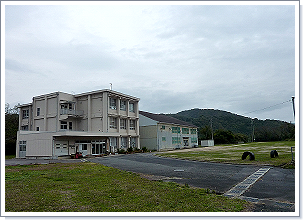伯耆国 河村郡
まつざきじょう
松崎城

所在地
鳥取県東伯郡湯梨浜町松崎
城 名
まつざきじょう
松崎城
別 名
まつがさきじょう
松ヶ崎城
伯耆民談記での記述
きぎょうがさきじょう
亀形ヶ鼻城
城山が亀甲形で本丸周辺が先端(鼻)にあたることに因む呼称
築城主
小森氏(南条氏の与力とする)
築城年
不詳
廃城年
1600年(慶長5年)
形 態
海城、丘城
遺 構
郭跡※、空堀※、石垣※
※ 校舎建設の際に改変及び攪乱とする
※ 主郭東側で現在の堀の内団地周辺とする
※ 校舎建設の際に移された遺構で現在は校舎裏に石積みの状態で遺る
現 状
湯梨浜町立さくら工芸品工房(旧桜小学校)、宅地(堀の内団地)
備 考
史跡指定なし
縄張図
松崎城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供
参考資料(史料及び文献、郷土史など)
陰徳太平記[香川正矩 編](明治44年5月 犬山仙之助)
伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)
伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)
伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)
因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)
因伯古城跡図志下 伯耆国(文政元年 鳥取藩)
因伯地理志(享保11年)
東郷町誌(昭和62年12月発行 東郷町誌編さん委員会)
年 表
不明
南条氏の与力であった小森氏による築城を伝える。
1580年
天正8年
1581年
天正9年
1600年
慶長5年
関ヶ原の戦いで西軍に与した南条氏が改易されると伯耆国羽衣石城は廃城となり、当城も併せて廃城と伝える。
概 略
東郷湖の東側に位置し、湖上を一望できる字「城山」に所在する。
現在は字「城山」及び字「西の丸」周辺が湯梨浜町立さくら工芸品工房(旧桜小学校)、字「堀」が宅地(堀の内団地)となっている。
学校跡の敷地の北東端(主郭中央の北側)には整地の際に出土した石垣が積まれ、元々は南東部から出土したと案内板にあるが中世末期~近世初期の石垣と考えられている。
旧桜小学校建設に伴い以降の殆どが改変或いは攪乱されており、現地案内板には別名を「亀形ヶ鼻城(きぎょうがさきじょう)」としている。
別名の由来は城域が亀甲型をしており、本丸(主郭)の位置が東郷湖に面した鼻(さき)にあたるためとしている。本丸(主郭)を「鼻」とする場合、松崎神社周辺(伯耆国蝶山砦)も同一の城砦に含まれるとも推測される。
築城時期は不詳とするが南条氏の与力であった小森氏の築城を伝える。
因伯地理志(東郷町誌より)
山面南、南為大手。高九間(約16メートル)、城内南北四町(約440メートル)、東西二町五十間(約310メートル)畠地也。有高下也。城中無水、下本丸一町五十間(約200メートル)、有井水多(略)
東郷町誌
南条氏の与力が城居したと伝えられる。字「城山」「西の丸」「堀」の地名がある。「城山」と「西の丸」とは数メートル程の段差があったが桜小学校建築のため整地された。「城山」の東に字「堀」があり現在の「堀の内団地」のあたりと考えられる。
東郷町誌では「伯耆民談記」と「因伯地理志」からの引用に補足を加え、現状についての記述が見える。
南条氏の与力であった小森方高の居城とし「因伯地理志」に記述の「下本丸」を西の丸、「城中無水」との記述から城山東側の堀は空堀であったと推測している。
伯耆民談記 巻之第十二 河村郡古城之部 松ヶ崎の城の事
当城には南条の与力小森和泉守方高居住せり。天正八年、伯耆守籠城によって和泉守も同籠せしが元来山田出雲と入魂なる故、山田逆意を企て高野宮夜討の後は南条を始め諸人何となう心を置けり。八橋の杉原彌三郎元盛是を聞て密かに小森方へ使者を遣わし味方に引入れんと勧めたりけるに和泉やがて同意しけるが返り忠の手始めに東郷小鹿谷上山を固め進ノ下総が陣處に夜討の事を彌三郎に内通す。和泉が属兵の中に下総と入魂の者ありて此者件の密計を下総に告げし故、頓て是旨本城へ注進せり。南条驚き家老の輩を呼び集め内談一決して下総が陣処へ加勢を遣わし大砲を合図に定め待ちたりける處に和泉は謀計の洩れたるをば夢にも知らず杉原より加勢を乞い、同年九月廿日の夜、二百余人忍び寄り伺いけるに陣中物静かにて沈睡の体に見えたり。和泉思いけるは此處を行過ぎて長山の陣、海老名源助、小森弾正、一條宅間等が小屋に放火し、附入りて本城に切入りなば一挙して大功を立つべしと俄かに分別を変え、其旨を部下の輩と談合すれども士卒更に同心せず。兎角する處に下総が陣中より大筒を打出し、軍兵潮の涌くが如くに切り出でければ寄手仰天して色めく處を合図はよしと長山陣より海老名等の軍兵真下りに突てかかる。野花坂を固めたる相賀柵之助が人数も加わり其外谷々所々の諸卒一時に起り立ち八方より揉合せければ寄手散々に打負け百余人討死したりける。残る者どもあけに染って別所谷の方へ敗軍す。和泉は士卒を励ましけれど、もり返すべき様はなく諸共に別處谷の方へ落行きたるが別所谷は知行所なれば名主某が宅に駈入りしを下総追詰て討取りたり。さて首は下総より本城へ送り実検に備えしと云う。此時別所村の百姓共和泉が死骸を乞い、厚く葬りたるが村端の森の中に今猶塚有り。さて此役に下総が功を抜群なりとて南条大に感賞し松ヶ崎の城を与え東郷の守護とせり。天正の末、東郷山公事ありし時に守護進ノ下総免之と書ける裁訴状あり。今に至て之れを伝うものあり。慶長五年、関ヶ原の役に南条家滅亡に依て当城も羽衣石と等しく破滅せられ今唯名のみ残れり。
1580年10月20日(天正8年9月20日)
南条方の城番であった小森方高が毛利方の杉原元盛に内通し南条方を離反する。
小森方高は寝返りが偽りでない事を証明するため小鹿谷の上山(伯耆国上山砦)に布陣していた進免之への攻撃を画策する。
杉原元盛への援軍要請も取り付け、小森方高は同日夜半に進免之の陣所へ闇討ちを仕掛けたが、夜討の計画は進免之へと漏れていた上、当初の作戦行動から逸脱した方針を示したため将兵の理解を得られず、部隊が混乱した所を南条方の逆襲に遭い100名余りの戦死者を出している。
小森方高は敗残兵をまとめ別所谷方面へと落延びたが、進免之の追撃を受け討ち取られたとする。
首級は首実検のため羽衣石城へと送られ、遺骸は別所村の百姓によって弔われたとする。
当城と併せ、小森方高の知行所は進免之へと引き継がれ、関ヶ原の戦いで南条家が改易されるまで城主を務めたとされるが、陰徳太平記では1581年(天正9年)の吉川元春(馬ノ山砦)と羽柴秀吉(御冠山陣)が対峙(馬ノ山の対陣)した際は毛利方の小森久綱が在番している。
1600年(慶長5年)頃
関ヶ原の合戦の戦後処理では西軍に与した南条家の改易と合わせ、居城の羽衣石城や他の支城と同じく廃城とされる。 (伯耆民談記)
写 真
2014年11月1日