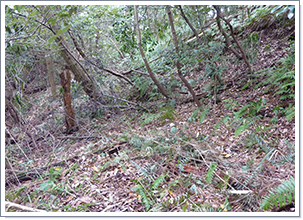伯耆国 汗入郡
きたおじょう
北尾城

所在地
鳥取県米子市淀江町福岡
城 名
きたおじょう
北尾城
所在した北尾村の村名に因む
別 名
たかおじょう
高尾城
宇田川村史での記述
たかおたにじょう
高尾谷城
淀江風土記での記述
築城主
不詳
築城年
不詳
廃城年
不詳
形 態
山城
遺 構
郭跡、堀切、土塁、土橋、竪堀、虎口、井戸跡、礎石、水路跡
現 状
山林
備 考
史跡指定なし
縄張図
北尾城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供
※鐘付堂の縄張図 主郭などの縄張は淀江町誌に図示あり。
参考資料(史料及び文献、郷土史など)
御巡見様御廻手鏡(1710年 宝永七年寅ノ年の編)
汗入川西神社改帳(正徳六年(1716年))
陰徳太平記[香川正矩 編](明治44年5月 犬山仙之助)
宇田川村史(大正4年9月 鳥取縣西伯郡宇田川村役場 足立正編)
武崎神社存置稟請(大正4年10月27日)
汗入史綱(昭和12年9月 国史研究部 本田皎)
淀江町誌(昭和60年8月 淀江町)
町政百周年記念 淀江風土記(平成元年12月 淀江町役場)
年 表
戦国時代
高尾谷より水道が通じる要衝を福頼元秀が守備とする。
概 略
旧北尾村山中の字「要害(えいぎゃ)」及び字「山要害(やまえいぎゃ)」に所在し、福頼左衛門(福頼元秀)の居城としている。
旧村名の由来は北の山の尾根に所在したことに因むとしており、1877年(明治10年)に上淀村と合併し福岡村となったが北尾の地名は現在も残っている。
西から北西側の高尾谷(たかおだん)、北東から東側の日当平(ひなたびら)の谷部を天然の要害に利用していたと推測され、城主などの居館は詰城の南西側に置かれていたと推測される。
居館に関する字名には「空屋敷(そらんだ)」「村屋敷」「土居の屋敷(でいのやしき)」が見える。
城域規模は不明だが、字「塔ヶ谷(とうだだん)」の途中から土橋状の帯郭と土塁のような土盛が見え始め、尾根を断ち切る形で幾条もの堀切が存在する。
道中の土塁に関しては古道の名残とする話もあり、大正時代に高尾池の溜池ができた後は山中に新田と言われる開墾地が作られ、さつまいもなどを栽培していたとされることから農道の名残とも考えられる。
御巡見様御廻手鏡 古城跡の条 北尾村の項
古城主不知。
御巡見様御廻手鏡(宝永七年寅ノ年の編)では北尾村に古城跡の存在を記すが城主は不明とする。
町政百周年記念 淀江風土記 北尾村の条
淀江風土記では高尾谷に所在した古城について城主を福頼氏と伝え、墓所の存在も併記している。
墓所は伝承にある藤兵衛塚(トーベー塚)を示すと考えられ、城主の福頼氏は福頼藤兵衛と推定される。
藤兵衛塚は福頼塚とも呼ばれ、伯耆国香原山城の合戦において福頼氏(福頼左衛門或いは福頼藤兵衛)が射殺された場所と伝えられる。
宇田川村史 福岡村の条(一部抜粋)
本村内に城山、要害、山要害などの小字地名現存す。城跡を高尾と呼び、高尾谷の上に兀立す。
福頼左衛門、高尾谷より水道を通じ此城を死守。敵将(行松)はトヨなる老婆を捕え尋問し、城山の西の火打山より森林中に暗渠あり。ここより水を引くと教える。
宇田川村史では高尾の山頂部に城跡が所在したとし、高尾谷から見上げると飛び抜けて高い位置に所在したと表現している。
淀江町誌にも宇田川村史から引用する形で同様の記述が見えるが双方ともに香原山城を当城砦と推定し、天正年間の香原山城周辺における合戦内容の一部に伯耆国稲吉城に伝わる伝承と酷似した描写が添えられている。
当城砦で起きたとする香原山城の合戦では毛利方の山城として登場し、南条方に与した行松氏の軍勢に攻められ水源であったトヨヶ口(トヨの口)を抑えられている。
水の確保に窮した城主の福頼左衛門(福頼元秀)は白米を水に見立てて愛馬を洗って見せるなど水不足を偽装したと伝える。
水源のトヨヶ口からは山裾を這うように城内へと続く水路が引かれていたと伝え、伝承にも暗渠であったとしているが、トヨヶ口と主郭付近の標高が同じことから稲吉城のように暗渠の配水路が用いられたとするかは不明。
現在の等高線で比較する場合、主郭部分は水源より標高が高く、高低差を同じとする場合は鐘突堂の方へ水路が回っていたとも考えられ、鐘突堂が水ノ手井戸などを備えていたことが推測される。
北尾村から東の山中には合戦で討死した福頼藤兵衛の首塚と伝わる場所が存在し、慰霊のための五輪塔が建立されていたとされるが、現在は武崎神社の境内に移されており元来の所在地は不明とする。
城砦の規模では香原山城に劣るが防御施設の普請は明らかに手が込んでいる。
太古は麓の上淀廃寺跡に寺院が置かれ、直下の淀江平野は古代山陰道が通っていた推定地のひとつに挙げられることから交通の便もよく、伯耆国尾高城との連携も容易であり、近くの天神垣神社には吉川元長による再建の伝承もあることから地理的にも重要な拠点であったことが伺える。
鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編)に掲載の縄張図は本丸から南西に位置する鐘突堂と呼ばれる場所であり、当城の主郭周辺の縄張図は淀江町誌に掲載されている。
武崎神社存置稟請(大正四年十月二十七日)
武崎神社存置稟請の神社由緒では空屋敷を福頼氏の居館としている。
汗入川西神社改帳(正徳六年)
一、武崎神社 村より下 田畑の中
一、王子権現 晩田山平中
一、福頼大明神 五輪塔あり 村より東の山
汗入川西神社改帳では当時の神社や祠など凡その位置が記入されているが福頼大明神の正確な所在は不明とする。
武崎神社の松と藤兵衛塚(トーベー塚)の松は同じ頃の時代のものとしている。
写 真
2021年5月14日
遠望
トヨヶ口
鐘突堂
土塁
堀切
堀切
眺望
眺望
眺望
南大堀切
南大堀切
南大堀切
主郭
主郭
主郭
主郭
主郭
主郭(井戸跡)
主郭(井戸跡)
主郭(堀切)
主郭(堀切)
主郭
主郭
主郭
主郭(土橋)
主郭(土橋)
主郭(堀切)
主郭(堀切)
主郭(堀切)
主郭(北の郭)
主郭(北の郭)
2013年12月25日、2014年12月21日