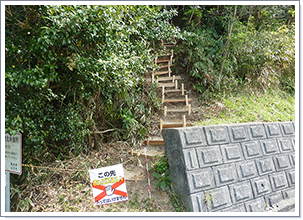伯耆国 会見郡
いしいじょう
石井城

所在地
鳥取県米子市石井(字要害)
城 名
いしいじょう
石井城
伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)の記述
別 名
いしいようがい
石井要害
石井村田畑地続字限絵図に記述
いしいのとりで
石井砦
八幡神社周辺の狭い範囲の呼称
はちまんじょう
八幡城
鎮座する八幡さんに因んだ呼称で延宝六歳石井村水帳写に「はちまん」とある
築城主
山中幸盛
尼子再興戦での築城を伝える
築城年
不詳(鎌倉時代)
廃城年
不詳
形 態
連郭式平山城
遺 構
郭跡※、空堀(横堀)、切岸※、土塁※、土坑※、土壁※、井戸跡※、水濠※
※ 石井地区単県急傾斜地崩壊対策事業により改変及び消滅
※ 且つて主郭に所在したと伝わるが消滅
※ 上層の郭や土塁を平削し堀を埋め立てて田圃へ改変
現 状
八幡神社、山林、宅地
備 考
史跡指定なし
縄張図
石井要害略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供
絵 図
石井村田畑地続字限絵図 ※米子市教育委員会提供
参考資料(史料及び文献、郷土史など)
伯耆志(因伯叢書 伯耆志巻二 大正5年8月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
因伯古城跡図志下 伯耆国(文政元年 鳥取藩)
陰徳太平記[香川正矩 編](明治44年5月 犬山仙之助)
伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)
伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)
伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)
因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)
萩藩閥閲録(山田家文書他)
石井村名寄帳(元禄2年)
文政郡郷帳(文政年間 米子市談 第三巻より)
延宝六歳石井村水帳写(延宝6年 旧成実村史より)
石井村田畑地続字限絵図 字要害図(明治2年)
牧野家古文書(成実の歴史より)
紀氏譜記(日吉津村誌収録)
米子の歴史(昭和42年8月 伯耆文化研究会)
米子市談 第三巻(昭和48年7月~昭和50年5月)
旧成実村史(昭和39年3月 なるみ第22号)
成実の歴史(昭和61年3月25日)
一般財団法人米子市文化財団 埋蔵文化財発掘調査報告書16 石井要害跡Ⅰ(平成31年3月 一般財団法人米子市文化財団)
一般財団法人米子市文化財団 埋蔵文化財発掘調査報告書17 石井要害跡Ⅱ(平成31年3月 一般財団法人米子市文化財団)
年 表
鎌倉時代
在地土豪の居館が始まりと推定される。
法勝寺往来を監視し、有事の際には相対する伯耆国七尾城と共に防衛を担った要衝と伝わる。
不明
伯耆山名氏に仕えた伯州衆、片山高綱の居城と伝える。
大永年間
概 略
出雲との国境に程近い米子平野西端の独立丘陵上(字要害)に所在する。
古くは鎌倉時代頃の在地土豪居館が始まりと伝えているが記録に乏しい。
伯耆国七尾城、伯耆国奥谷城、伯耆国石井屋敷などの周辺諸城と連携し、出雲国や法勝寺方面から伯耆国尾高城へと続く街道往来の監視を担ったことは所在する立地からも推定され、郷土史料や口伝にも伝えられる。
城砦が所在したとされる丘陵は1964年(昭和44年)の宅地造成により、現在の八幡神社が鎮座する南東部の出丸と伝わる丘陵の一部を残し城域内の殆どの部分が消滅している。
出丸の残存部も度重なる改変や崩落を受け原型を留めていないと推定され、2018年(平成30年)には石井地区単県急傾斜地崩壊対策事業により八幡神社の鎮座する丘陵の急傾斜地が全方位削られ、2019年(平成31年/令和元年)には遺構のほぼ全てが消滅した。
標高29.4m、比高20m(※2018年の状態)は改変を受けた後の高さであり、宅地造成以前にも戦国期の郭拡張(八幡神社直下の南腰郭など)や廃城後(戦国末期~江戸時代始め)の農地拡張による空堀、水濠埋立のため、北側に所在した主郭など上段部から切り崩され標高も徐々に下がっていったことが推定され、往古は七尾城と並ぶほどではないにしても因伯古城跡図志(伯耆国)に並んで描かれる程度の高さを持った城砦であったと推測される。
石井で城砦に関連のありそうな小字名として「要害」「上高城」「下高城」「高城田」「陣場ドウドウ」「市場」が検出される。
石井村名寄帳(旧成実村史より)
そとぼり中田 壹畝弐拾歩
内ぼり下々田 弐畝九歩
ほり開下々田 参歩
石井村名寄帳では「そと堀中田」「内ほり下々田」「ほり開下々田」など堀を水田に転用した字名が見え、上段西の方に「井戸跡」、東方二段目の所を「昇りの段」、上段東南の所を「枡形」としている。
延宝六歳石井村水帳写(旧成実村史より)
八まん 六畝弐拾参歩
本丸 壹反参畝拾歩
デ丸 五畝廿六歩
延宝六歳石井村水帳写では「本丸」「デ丸」「八まん」の字名が見えるとあり、本丸は西の広い方、出丸は八幡神社の南隣、表道は巽の方、裏道は南の方に所在としている。
文政郡郷帳(米子市談 第三巻より)では「八幡宮あり。石井山妙喜寺あり。村より東北にあって木引因幡守古城跡あり」とある。
旧成実村史では当要害の見張砦として奥谷城(外構山・船上山とも)、字ドウドウの南側の山(西谷山)、旧成実小学校南側(河屋山)の3つを挙げている。
1496年(明応5年)頃
赤松政則と離縁した紀成盛の娘が伯州へ戻る際に随行した人物として古曳永綱の名が見え、紀氏譜記では古曳永綱の居住としている。
牧野家古文書では1530年(享禄3年)頃出来事とされる。
伯耆民談記 石井城之事の条(昭和35年3月 萩原直正校註)
宗像庄石井村にあり。古城主片山小四郎領地なり。
伯耆志 石井村の条 要害の項
村の東北田中の山なり。八幡の小祠あり。片山小四郎という人の城なりと云えり。伝詳かならず。
伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)では「石井城之事の条」、伯耆志では「石井村の条 要害の件」に記述が見える。
伯耆志の挿絵「捜図」では丘陵頂部から3段に平削された郭が連なる連郭式城砦の名残が描かれている。
絵図の郭には建物の図示が見えず、伯耆志の成立時には記述の通り既に城砦としての機能は失われ小祠や田畑へ改変されていたことが伺える。
石井村田畑地続字限絵図 十、字要害(明治2年)からは北西側の最も高い郭が主郭と推測でき、二段目の北側、東側に帯状腰郭と南側に切岸(或いは堀切)を隔てて現在の八幡神社が鎮座する出丸が配され主郭の防御を担ったと考えられる。
三段目の西側、北側、東側を囲むように帯郭状腰郭と防柵を配し、南側には特に高低差を持った切岸で防御を高めた構造が伺える。
また、周囲を囲む水田はかつての水掘を埋め立てて造成された水濠の名残とされ、加茂川から水を引き込み水堀を周囲に張り巡らせた水濠要塞であったことが推測される。
当城砦はいくつかの時代で改修が繰り返されたことが発掘調査から判っており、鎌倉時代から戦国時代にかけて土坑の埋立や郭の造成、拡張(戦に特化した改修)、戦国時代から江戸時代にかけて田畑、祠への郭の拡張、転用(戦ではなく生産性向上のための改修)が行われ、時代によって姿を変えていったことが推測されている。
城主は片山小四郎の居城を伝える。
片山小四郎は尼子方に与した武将として記述されるが毛利方に与した片山平左衛門を同一人物とする説もあり、伯耆国手間要害周辺への焼き討ちに関しては攻撃対象が正反対になるなど一部記述に混同が見られる。
鎌倉時代頃から片山氏の一族がこの地に地盤を持っていたのかは不明であるものの、伯耆山名氏が伯耆国を支配した頃の在地有力国人衆(伯州衆)の中に片山氏の名が見える。
室町時代~戦国時代にかけては伯耆山名氏の下で当地を治め、尼子氏が伯耆国で台頭すると但馬山名氏を頼って但馬国へ退去した派閥と、尼子氏へ属し当地へ留まった派閥があったと考えられる。
1588年(天正16年)
西伯耆から尼子氏が駆逐され、毛利氏の統治に移ると片山氏は所領を奪われるなどした後に名が見えなくなり、古曳吉種が城番に置かれている。
古曳吉種は地元郷土史や個人所有の文書では城砦建築の名人とあり、当城を水濠要塞として設計し築き上げた人物と伝わる。
この知識と経験を同時期に領有した伯耆国戸上城の法勝寺川に面した登り土塁へ転用、後に伯耆国米子城の中海に面した登り石垣の基礎として取り入れ中海や加茂川の水濠を用いて海城としての機能を高めた設計を行ったことが推測される。
写 真
2013年5月11日、2014年6月21日、2018年2月18日、2018年4月22日、2018年6月2日