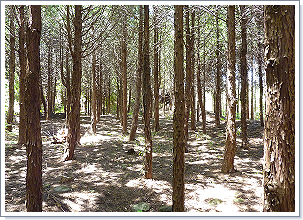伯耆国 汗入郡
とみながじょう
富長城

所在地
鳥取県西伯郡大山町富長
城 名
とみながじょう
富長城
富長村の所在に因む
築城主
築城年①
1331年~1334年(元弘年間) ※蒙古襲来に対して築かれたとする説
築城年②
1500年(明応年間)頃 ※福頼左衛門尉による増改築とする説
廃城年
1524年(大永4年)
形 態
平城、海城
遺 構
郭跡※、土塁※、平入虎口※、堀切※、切岸※、石垣
※ 富長神社へ改変
※ 空堀など損傷の激しい箇所は地元住民による修復としている
※ 密使門と伝える
現 状
富長神社、山林、道路
備 考
名和町指定文化財(現大山町指定文化財) 昭和57年11月19日指定
縄張図
富長城略測図(鳥取県中世城館分布調査報告書第2集(伯耆編))※鳥取県教育委員会提供
汗入史網で城主とする
参考資料(史料及び文献、郷土史など)
因伯古城跡図志下 伯耆国(文政元年 鳥取藩)
伯耆民諺記(寛保2年 松岡布政)
伯耆民諺記(写)(昭和23年 原田謙)
伯耆民談記 巻上(大正3年1月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民談記 巻下(大正3年3月 佐伯元吉 因伯叢書発行所)
伯耆民談記(昭和2年10月 佐伯元吉)
因伯文庫 伯耆民談記(昭和35年3月 萩原直正校註)
大山寺文書(応永廿九年)
富長神社由緒書( )
鳥取藩史( )
汗入史綱(昭和12年9月 国史研究部 本田皎)
汗東神社取調帳( )
ふるさと古城史⑯(佐々木 謙)
続名和町誌(平成22年 名和町誌編集委員会)
年 表
鎌倉時代
在地豪族の居館が所在と伝える。
1331年~1334年
元弘年間
室町時代~戦国期
福頼左右衛門尉の在城を伝える。
不明
現在の富長神社本殿周辺に陣屋が築かれ、城内には駒井刑部の「駒ノ馬屋」「馬飼場」があったと伝える。
概 略
主郭跡に富長神社が鎮座する。
文永の役(1274年(文永11年))、弘安の役(1281年(弘安4年))と二度にわたる蒙古襲来を受け、海岸線の防衛強化のために築城された一城が始まりではないかと推定されている。
因伯古城跡図志 富長村古城跡
富長村古城跡福頼左右門尉居城と申伝、当時社地となり森有。高三間計、前は往来也。近辺へ竹木有。前通に水有。後は直に海也。海辺より古城近の高兀二十間位。三方へ堀形有。
西 長六十間位、横五十間位、廻り土手築上。
南 (長)四 十間位、(横)三十間位。
文政元年の因伯古城跡図志には富長村古城跡として図示と概要の記述が見える。
城主に福頼左右門尉と見えるが、伯耆国米子城(飯山城)の城主とされる福頼元秀ではなく、国信村の字「左右衛門屋敷」に居住した福頼左右衛門尉か、福頼元秀の六男で留長村(富長村)に出張し館を構えたとする村上新三郎と推定される。
汗入史網では名和氏の家臣、荒松兵庫の居城とされ、船上山の合戦では軍事拠点のひとつと推定している。
城容については北西隅の一段高い郭と土塁が物見台、社殿辺りが陣屋、北東隅が馬屋の跡(駒ノ馬屋)としている。
大山寺文書では名和氏没落後は伯耆山名氏配下、福頼沙弥の支配地とされ、1524年(大永4年)の大永の五月崩れまでは福頼氏が当城周辺を治めたと推測される。
※大永の五月崩れの後、福頼氏は尼子氏に降伏した説と、降らず国外に退去したとする説がある。
御巡見様御廻手鏡 富長村の条
古城壹ヶ所城主福頼左衛門尉
御巡見様御廻手鏡には城主を福頼左衛門尉としているが、こちらも福頼左右衛門尉が推測される。
主郭に鎮座する現在の富長神社の社殿は1659年(万治2年)に町内の古御堂部落にあったものを移築したとある。
神社本殿には陣屋があったとされ、北東には駒井刑部の駒の馬屋、馬飼場があったと伝わる。
廃城年は1524年(大永4年)、大永の五月崩れに伴うと推定されている。
廃城から神社が移築されるまでの間、畑などの改変は行われなかったとしている。
西側の虎口は昭和50年代中頃に車の出入口を設けるために破壊され、その土で堀を埋めたとしている。(続名和町誌)
写 真
2013年5月17日、2014年9月21日